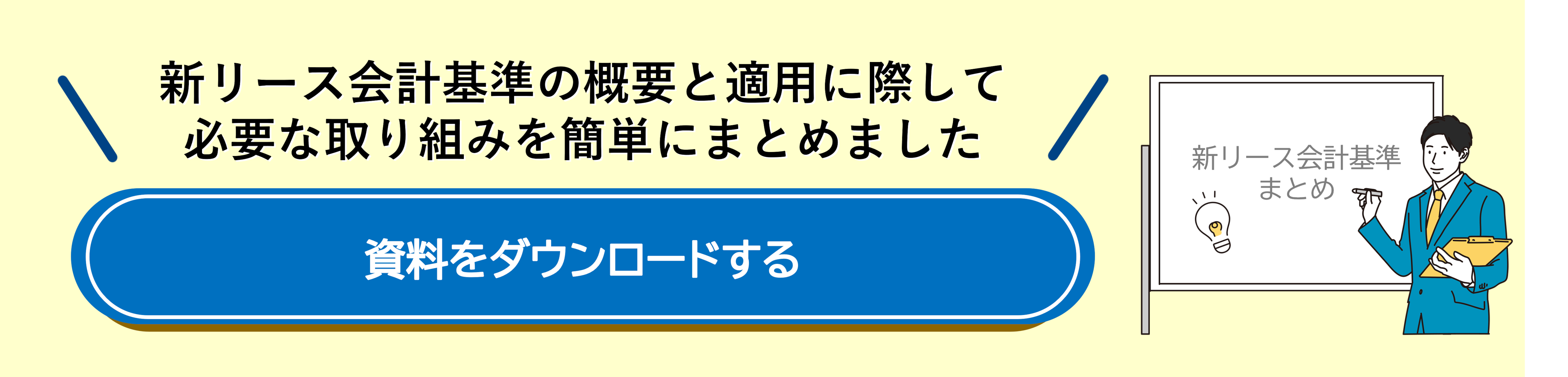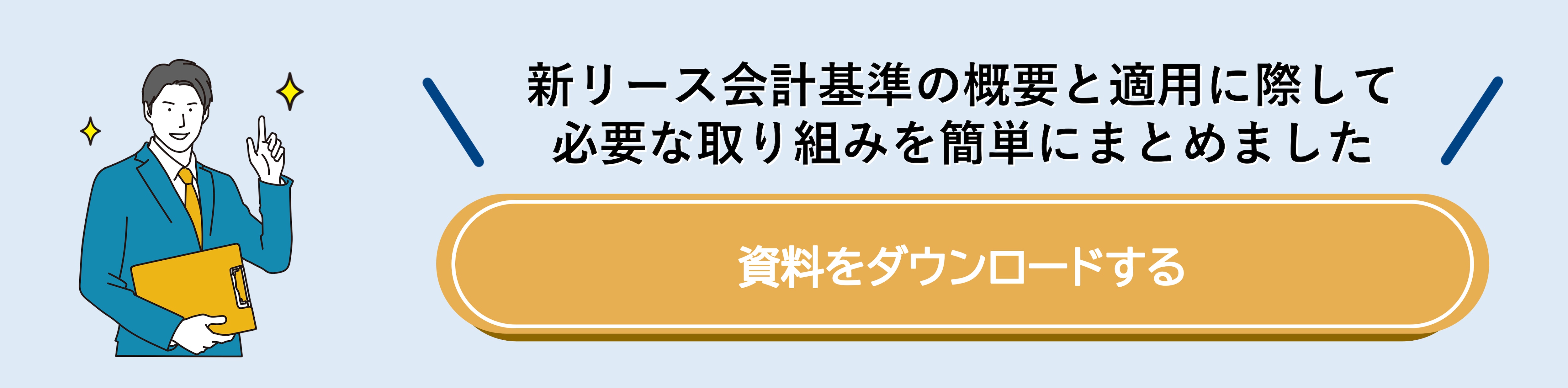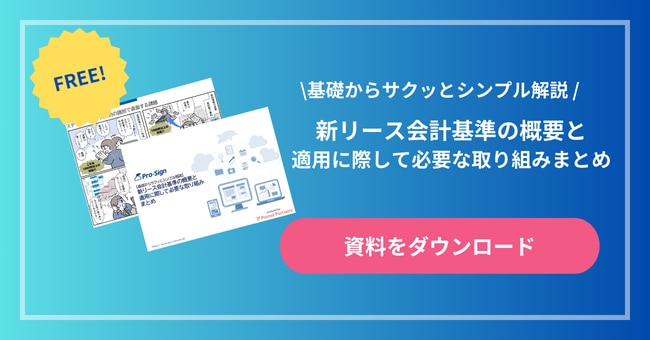契約と資産のズレで監査に止められる!リース会計の現場あるある

新リース会計基準の適用が2027年に迫り、多くの企業で「思わぬ落とし穴」に直面しています。
契約書の内容は把握しているにもかかわらず
資産計上や会計処理にどうつながっているか追えない
更新や解約の情報がどこかで途切れ、会計上の数字と契約内容にズレが生じる
そんな状況に陥り、“迷子”になってしまうケースが後を絶ちません。
背景にあるのは「契約は法務・総務、資産は経理・財務」といった縦割り組織の構造。
これまでは何とか乗り切れていたこの分断が、新リース会計基準によって白日の下に晒されているのです。
なぜ“狭間”が生まれるのか
企業の中で契約を扱う部門と資産を扱う部門は、そもそも立場も目的も異なるため、注目する視点が根本的にずれています。
- 契約管理の視点:契約条項、更新日、解約条件、違約金、法的リスクなど
- 資産管理の視点:減価償却の方法、利用期間、会計仕訳、税務影響、監査対応など
たとえば、法務や総務は
「契約の内容に抜け漏れがないか」
「企業に不利な条項が含まれていないか」
といった契約リスクの最小化に注力します。
更新や解約のタイミングを正しく把握しているかどうかが彼らの評価軸になります。
一方で、経理や財務は
「この契約に基づく資産をどの金額で計上すべきか」
「どの期間にわたって費用を認識すべきか」
という会計数値の正確性を最も重視します。
つまり、同じ契約書を前にしても、法務・総務は“文言と条件”を、経理・財務は“数字と仕訳”を見ているのです。
視点が違うため、双方は「同じものを見ているつもりで、実は全く違う情報に着目している」という状態が生まれます。
さらに問題を複雑にするのが、情報の伝達経路です。
契約書はPDFや紙で保存され、資産台帳はExcelや会計システムに入力される。
別々のフォーマット、別々の担当者が扱うため、契約と会計の情報がシームレスにつながらず、どこかで齟齬が発生してしまいます。
現場担当者が「口頭で聞いた」「メールで共有された」といった断片的な情報に頼ることも多く、内部統制の観点から見れば非常に脆弱な状態です。
従来は、このような断絶があっても「担当者の経験」や「属人的な調整」で何とか埋め合わせができていました。
しかし、新リース会計基準が適用されると、契約ごとにリース期間やオプション条項を正確に資産評価へ反映させる必要が生じます。
属人的な“場当たり対応”では追いつかなくなり、問題が一気に表面化したのです。
結果として、契約 → 資産 → 会計という流れの一貫性が崩れ、正確な会計処理やスムーズな監査対応が困難になります。
これは単なる「作業の手間」の問題ではなく、企業のガバナンスや内部統制に直結する大きなリスク要因と言えるでしょう。
実務で起きる“迷子”の典型例

実際の現場では、契約と資産の情報が断絶しているために、日常的に“迷子”が発生しています。以下に代表的なパターンを挙げてみましょう。
①契約更新や解約情報が本部に共有されない
現場店舗や営業部門が更新・解約手続きを進めても、その情報が本部に届かず、資産台帳に反映されないことがあります。
結果として、会計上の利用期間と実際の契約期間が食い違い、
「利用していないはずの資産が残っている」
「もう更新済みなのに契約が終了扱いになっている」
「既に存在しない資産が計上されている」
といった不整合が発生します。
特に多店舗展開企業では、この“情報の遅延”が連鎖的に広がりやすいのが特徴です。
②契約書PDFと会計システムが完全に別世界
多くの企業では、契約書はファイルサーバやクラウドにPDFで保管され、一方で資産や仕訳は会計システムに入力されます。
両者がシステム的にリンクしていないため、監査人から「この数字の根拠となる契約書を示してください」と問われたときに、すぐに答えられないのです。
担当者が過去のメールやフォルダを探し回り、最終的に監査用フォルダを作り直す――この光景は、多くの経理担当者にとって“あるある”ではないでしょうか。
③社内の認識のズレが“二重計上”や“未計上”を招く
営業部門が契約を結んだつもりでも、本部の法務が承認していなければ正式な契約と見なされず、経理に届かないケースもあります。
その結果、契約したのに資産計上が漏れる、あるいは逆に同じ契約を二重に登録してしまう、といった事態が起こります。
④更新や解約のタイミングが曖昧
特にリース契約は「自動更新条項」や「オプション条項」が含まれることが多く、更新意思の有無によってリース期間が変わります。
この判断が現場任せになっていると、経理側では「どの期間で資産計上すべきか」が分からず、棚卸しのたびに混乱が生じます。
こうしたケース、「自社でも身に覚えがある…」と感じられる方は少なくないはずです。
一つひとつは小さな行き違いに見えても、それが積み重なれば決算スケジュール全体を圧迫し、監査対応を長引かせる要因となります。
しかも、修正のための社内調整や資料探しは担当者の大きな負担となり、通常業務を圧迫する「隠れコスト」にもつながります。
リスクの本質
表面的には数字が合っているように見えても、契約との対応関係を証明できなければ監査では指摘を受ける可能性があります。
監査法人が重視するのは単に「数字の正確さ」ではなく、「その数字が契約に裏付けられているか」という説明責任です。
リース会計では、契約内容に基づくリース期間やオプション条項の扱い、減価償却の計算など、数字の根拠が明確でなければ即座に疑義を持たれます。
さらに問題を深刻化させるのが、部門間のサイロ化です。
契約情報は法務や総務、資産情報は経理や財務と、情報が分断されることで、担当者に属人的な管理が集中しやすくなります。
- 「○○さんしか契約更新のタイミングを把握していない」
- 「△△さんが休暇中だと解約処理が止まってしまう」
こうした状態は監査リスクだけでなく、日常的な経営判断にも影響を及ぼします。
たとえば、資産の利用状況や契約コストの正確な把握ができなければ、投資判断や店舗展開の意思決定に遅れや誤判断が生じる可能性があります。
さらに、情報の二重管理や非効率なプロセスが放置されると、以下のような負の連鎖が起こります。
- 契約書と資産台帳の内容が食い違い、確認作業や修正作業に膨大な時間を費やす
- 不整合を是正するために過去の仕訳や契約履歴を遡り、追加作業が発生する
- 属人管理によって業務負荷が特定の担当者に集中し、人材流出やモチベーション低下の原因になる
このように、リース会計における“契約と数字の断絶”は、監査上のリスクにとどまらず、企業の成長スピードや経営判断の質にも影響を及ぼす根本的な問題なのです。
解決の方向性
契約と資産の断絶による“迷子状態”を解消するためには、契約と資産を一元的に紐づけて管理する仕組みの導入が不可欠です。
ここで重要なのは、「担当者の記憶や手作業」に依存せず、部門横断で正確な情報を共有できる環境を整えることです。
①共通の台帳を整備する
部門を超えて利用できる共通の台帳を持つことで、契約 → 資産 → 会計の流れを一本の線でつなげます。
これにより、営業が把握している契約情報と経理が把握している資産情報の間に齟齬が生じにくくなります。
また、契約の更新や解約のタイミングもリアルタイムで反映されるため、意思決定に必要な情報をすぐに確認できるようになります。
②システム活用による属人性排除
システムを活用すれば、履歴管理や自動仕訳が可能になり、担当者ごとの属人管理を排除できます。
契約情報と資産情報が自動でリンクされることで、情報の鮮度と正確性が保たれ、人的ミスや二重管理のリスクも大幅に軽減されます。
③監査対応の効率化
監査時には、検索ひとつで契約と資産の対応関係を提示できるようになります。
これにより、監査人からの質問に即座に回答でき、従来のように契約書やメールをひっくり返す膨大な作業から解放されます。
結果として、監査対応の時間とコストを大幅に削減できるだけでなく、企業全体のガバナンス力も向上します。
つまり、「人に依存した管理」から「仕組みで担保する管理」へ移行することが、今後のリース会計対応には欠かせないのです。
さらに、仕組みを整えることで以下のような効果も期待できます。
- 契約と資産の情報が常に最新状態に保たれるため、経営判断のスピードと正確性が向上する
- 新しいリース契約や変更が発生しても、担当者に依存せず自動で会計仕訳に反映される
- 部門間のコミュニケーションが効率化され、二重管理や抜け漏れのリスクを減らす
このように、仕組みでの管理を実現することが、監査対応のみならず日常業務の効率化や経営判断の迅速化にも直結するのです。
まとめ
新リース会計基準は、これまで見過ごされてきた「契約管理」と「資産管理」の断絶を顕在化させました。
この分断を埋めることは監査対応を楽にするだけでなく、全社的なガバナンス強化や効率的な経営管理につながります。
「監査に止められたくない」「部門間で迷子になる状態から脱却したい」と感じる企業にとって、いまこそ仕組みを再構築する好機です。
そして、その一歩として:Pro-Sign
Pro-Signを活用することで、契約と資産を一元管理し、リース会計対応をスムーズに進められます。
部門をまたぐ“狭間”を埋め、監査においても自信をもって説明できる環境を整備することが可能です。
今後も続く会計基準対応・監査対応を、「属人」ではなく「仕組み」で乗り越えるために。
まずは Pro-Signの導入を検討してみませんか?