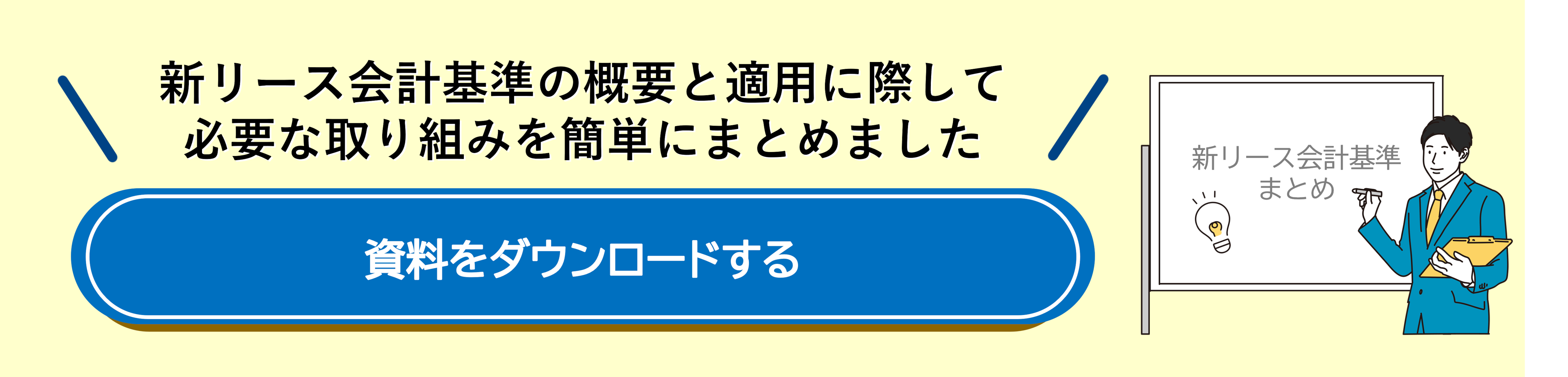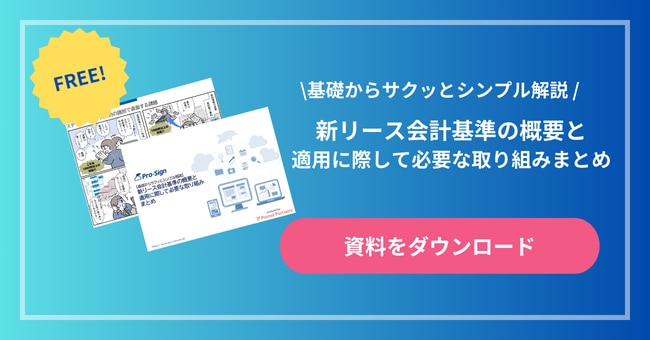新リース会計、準備万端だと思っていませんか? ― “契約の紐解き”という落とし穴

「新リース会計の対応、うちはもう大丈夫」と思っていませんか?
多くの企業では、固定資産管理システムや契約書管理システムを導入し、「これで準備万端」と判断しているケースが見受けられます。
しかし、実際に新リース会計基準の対応に取り組んでいる現場の声を拾っていくと、次々に浮かび上がってくるのが、“見えない実務負担”の存在です。
特に見過ごされがちなのが、「契約の洗い出し」や「賃料改定の整理」「会計データへの落とし込み」といった工程。
これらはシステムでは補えないアナログな作業が多く、対応に着手してから“想像以上に大変だった”と気づく企業も少なくありません。
新リース会計基準で求められる“実務”とは?
今回のリース会計基準の変更は、単なる会計処理ルールの見直しではありません。
企業が結んでいる様々な契約の中から、“リースとみなされるもの”を見極め、負債計上や資産認識の対象とするという、非常に実務的な判断が求められる基準です。
リース判定のためには、以下のような契約情報を精査し、数値に落とし込む必要があります。
- 賃料の金額とその内訳(原則賃料・変動賃料・償却補償金等)
- リース期間や延長・中途解約の条件
- オプション条項や特約事項の有無
こうした情報は、契約書を“読む”だけでは不十分です。
条文を正確に解釈し、数値化・構造化して、初めてリースか否かの判断が可能になります。
つまり、専門知識に基づく“翻訳力”と“変換力”が不可欠なのです。
既存システムだけでは越えられない「3つの壁」

①契約書の洗い出し
リース会計対応の第一歩は、対象となる契約の網羅的な洗い出しです。
しかし現実には、契約書が部署ごと・支店ごとにバラバラに保管されていたり、物件の更新により古い契約書と混在していたりと、全体像の把握だけでも相当な労力がかかります。
特に多店舗展開企業では、保有する物件数・契約書数が膨大になるため、1件ごとの確認作業が大きな負担となります。
たとえば、100店舗展開していれば100件の契約があるとは限らず、契約更新や再契約により1店舗あたり複数の契約書が存在するケースがほとんどです。
さらに、ファイリングルールや命名規則が店舗ごとに異なっていることも多く、Excel台帳と実際の契約書を紐づける作業だけでも混乱を招きがちです。
担当者が異動・退職していて管理の引き継ぎがされていなかったり、紙でしか保管されていない契約書が残っていたりと、対応の初期段階から課題が山積しているのが実情です。
つまり、「そもそも何があるかがわからない」状態からのスタートとなるケースも少なくなく、網羅的な洗い出しをするだけでも膨大な工数が発生することになります。
②リース判定の情報不足
契約書管理システムに契約書をPDFで保存していたとしても、それだけでは“リースかどうか”を判断するための情報を十分に得ることはできません。
必要な情報――たとえば「延長オプションの有無」「中途解約の条件」「賃料の構造(固定・変動・償却補償など)」といった項目は、契約書の中に埋もれており、構造化されていないためシステムで自動的に抽出することはできません。
契約の種類も多岐にわたり、店舗の形態やオーナーとの契約条件ごとに契約内容が微妙に異なることがほとんどです。
A店舗は「定期借家契約」、B店舗は「普通借家契約」、C店舗は「転貸借契約」など、判定に必要な情報が毎回異なるため、テンプレート化もしづらく、属人化した読み込みが必要になります。
さらに、契約書本体だけでなく、社内稟議書、条件変更の覚書、更新通知書といった補足資料も判定材料として不可欠です。
これらの書類がバラバラに保管されている場合、情報を集約して正確にリース判定を行うには、相当の手間と専門的な読み解き力が必要になります。
③賃料改定の紐解き
長期契約の多い不動産リースでは、契約期間中に賃料が改定されるケースも多く見られます。
その都度、契約更新や条件変更が行われていれば、それらを時系列で正確に整理し、数値として会計データに反映する必要があります。
さらに、更新に際して「口頭合意」や「メールベース」で条件変更がなされていることも多く、契約書に反映されていない変更内容をどう扱うか、といった判断も発生します。
契約書に明記された条文も、たとえば「〇年ごとに賃料改定の可能性あり」といった曖昧な表現だった場合、実務上の取扱いを確認する必要があります。
こうした“改定の履歴と条文の解釈”を契約書ごとに行うことになるため、対応が後手に回れば回るほど、手戻りのリスクや会計処理の誤りが発生しやすくなります。
固定資産管理システムをすでに導入して、中には契約書管理システムでPDFや簡易的な情報の管理もされている企業もいますが、新リース会計基準に対応するためのこれらの作業は自動化できない領域なのです。
そして現場では、
- 「今ある固定資産管理システムの機能で、なんとかリース資産も扱えないか」
- 「いっそ、固定資産管理システム側に投資して、改修してしまおうか」
といった選択肢が主流となっています。
しかし――それでは本質的な課題は解決できません。
なぜなら、最終的に会計システムに連携するための“構造化されたデータ”は、契約書をひとつひとつ読み解いて作らなければならないからです。
契約書管理システムにはPDFファイルが並んでいるだけで、必要な情報が抽出され、整理された状態にはなっていません。
つまり、システムを補強しても、その前段の“契約の紐解き”をどうにかしない限り、根本的な実務負担は変わらないのです。
対応を誤ると何が起きるか?
一見、システムを整備して対応できているようでも、実際に会計データとして出力しようとした段階で「整合性が取れない」「必要な情報が足りない」といった問題に直面する企業が増えています。
これは、契約書がPDFのまま保管されていたり、リース判定の根拠が明文化されていなかったりと、「読み解き」と「数値化」の工程が曖昧なまま進められていることに起因します。
特に多店舗展開企業では、拠点ごとに契約条件が異なる上に、担当者や運用ルールもまちまちというケースが多く、企業全体で整合性のあるデータを揃えることが非常に困難です。
たとえば、同じように見える2つの物件契約でも、ある店舗では延長オプションが契約書に明記されており、別の店舗では覚書で取り交わされている――といったように、形式も内容もバラバラで、全契約を横並びで比較・検証するのが極めて煩雑になります。
こうした状態で会計監査のフェーズに入ると、
- 「このリース期間の根拠はどこに記載されていますか?」
- 「この金額は、どの契約書から計算されていますか?」
- 「この判断は、誰がどういう資料を基に行ったのですか?」
といった出所の明確化や説明責任を求められる場面が頻発します。
結果として、スケジュールの遅延や、急遽のデータ修正・再作業、さらには外部コンサルタントの支援が必要となり、本来不要だったはずのコストが膨らむケースも少なくありません。
場合によっては、決算そのものに影響を及ぼす可能性すらあります。
解決策:「Pro-Sign」で実務負担を軽減
こうした“契約の紐解き”という煩雑な作業に正面から向き合い、実務担当者の負担を大きく軽減するために開発されたのが、契約情報の構造化とリース資産管理に特化した「Pro-Sign」です。
Pro-Signは、単なるファイル保管・検索ツールではありません。
契約書に記載された情報をデータ化・構造化し、会計処理に必要な形で整えることを目的とした、まさに“新リース会計対応のための実務ツール”です。
店舗数が多ければ多いほど、契約の件数も膨大になり、情報のばらつき・管理の属人化・契約条件の多様化など、さまざまな問題が複雑に絡み合ってきます。
Pro-Signは、そうした多店舗企業特有の管理上の課題に対して、一元的・横断的に契約情報を整理・活用できる設計になっています。
- AIによる契約情報の抽出とリース判定複雑・長文な契約条項も、AIが条項の内容を網羅的に判定し、リースの該当性をスムーズに判断可能
- 過去の賃料改定や条件変更も含めた時系列の契約情報管理各店舗・拠点ごとに異なる契約書でも、時系列での条件変更や賃料改定を簡単に追跡できる仕組みを搭載
- リース資産・負債の自動計算と、会計システムへのデータ連携AIで抽出した必要情報をリース資産管理モジュールへ連携することで、資産・負債の自動計算及び仕訳データの出力までを自動化
これにより、「契約書を読む → 情報を拾う → 数値にする → 会計処理する」という一連の流れを効率化し、属人的な作業の削減と、データの正確性・再利用性を高めることができます。
PDFで保管された契約書をただの「ファイル」に留めず、データに変えることで、実務に直結する管理と判定が可能になるのです。
まとめ:対応したつもりが、対応漏れにならないために
新リース会計基準への対応では、単にシステムを導入するだけでは不十分です。
本当に求められているのは、契約を正しく読み解き、構造化されたデータとして整理し、会計処理に耐えうる形で活用できる体制を整えることです。
特に多店舗展開企業の場合、
- 店舗ごとに契約条件が異なる
- 契約管理のルールがバラバラ
- 契約数が膨大で、更新や改定の履歴も複雑
といった事情から、「洗い出し~会計連携まで」の一連の対応が想像以上に煩雑化しやすい傾向があります。
しかも、その多くは属人的な運用に頼っており、異動や退職が発生するとブラックボックス化するリスクすらはらんでいます。
Pro-Signは、こうした現場の“最後の一歩”に着目し、契約情報の構造化・一元管理・リース資産の可視化を通じて、実務の負担軽減と対応の正確性を同時に実現するツールです。
「対応したつもりが、対応漏れだった」とならないために――今こそ、自社の契約情報の管理体制を見直し、実務レベルでの“本当の対応完了”を目指す時です。
ぜひ一度、導入事例やトライアルを通じてその使いやすさをご体感ください。