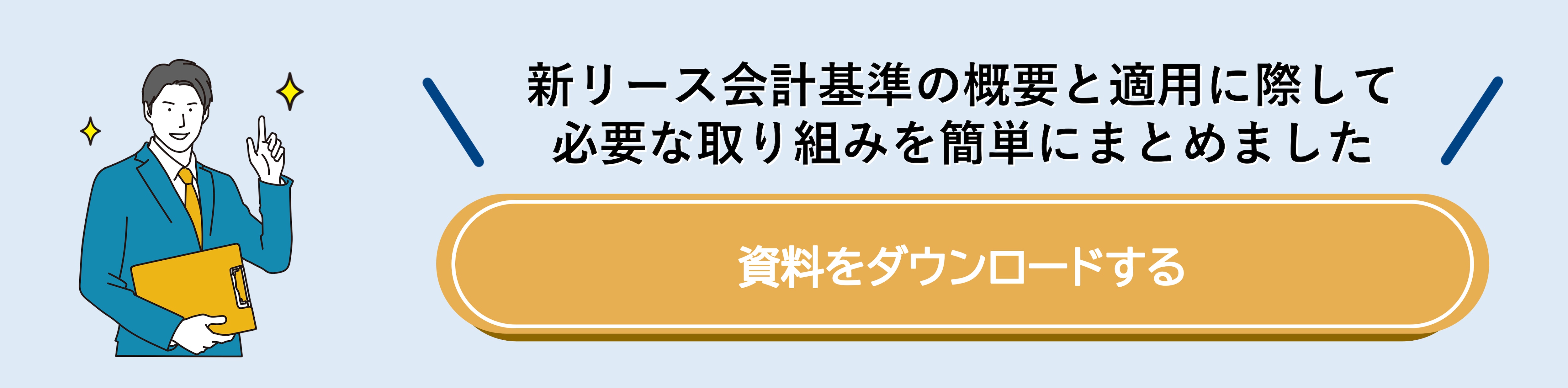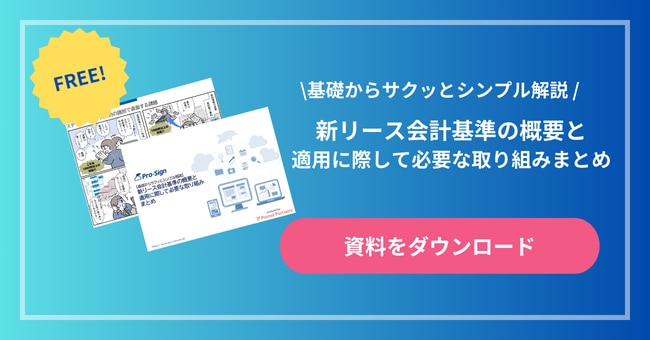新リース会計基準の基礎と賃貸借契約に与える影響について

多店舗や多事業所で事業を展開されている企業の皆様、新リース会計基準への対応準備は進めていらっしゃいますか。
「どういう影響があるのか、詳しく分かっていないけど企業会計基準委員会(ASBJ)の決定はまだだし、決まっても準備期間があるから大丈夫」とお考えの方がいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら、そんな簡単な話ではなさそうです。
会計基準の変更の話ですので、最終的には会計プロセスの変更が必要になるのですが、その前段階としての店舗情報管理が非常に重要だと言われています。
この記事では、新リース会計基準への対応の準備として重要だと言われている店舗情報管理について解説します。 なお、この記事では店舗、事業所、駐車場等、多店舗展開に関係する不動産を中心に構成していることをご了解ください。
目次[非表示]
新リース会計基準導入の背景
本題である「新リース会計基準への対応準備として行う店舗情報管理」の前に、新リース会計基準の概要を整理しておきたいと思います。
新リース会計基準は企業会計基準委員会(ASBJ)が提案しているもので、日本の会計基準のグローバル化の一環です。と言うのも、現行(2024年現在)の日本のリース会計基準は欧米が導入している標準的な考え方とは整合性が取れておらず、ガラパゴス化しているのです。
標準的な考え方とはIFRS第16号と呼ばれるもので、これに合わせることで、欧米の企業との経営状況の比較が容易になり、ひいては、日本企業の競争力を高めることにもつながります。
新基準公表がいつになるかは確定していませんが、公表されると、その2年後に強制適用が開始されると言われています。そして、専門家の間では「2024年度末に公表、2027年4月以降に始まる事業年度から強制適用」というシナリオが中心になっています。
つまり、新基準公表後の2年間の間に「新基準の対象となる物件の特定」「特定された対象による経営への影響の分析」「経営視点、監査視点での対応方法の検討」「会計プロセスの変更」「会計システムの変更」「運用のトライアルと調整」の全てを行い、強制適用に備えなければなりません。また、場合によっては、組織体制にまでも影響する可能性があります。
2年間の準備期間は、このような大きなプロジェクトを進めるために与えられる期間です。
決して、十分な期間だと言えるものではないと考えたほうがよさそうです。
なお、新リース会計基準適用の対象の企業は「上場企業およびその子会社、関連会社」、「会社法上の大会社(資本金5億円以上、または負債総額200億以上)」です。
新リース会計基準の重要ポイント
次に、新リース会計基準の概要についておさらいしておきます。
多店舗展開企業にとって、重要なポイントは次の3つだと考えられます。
- リース会計を行う対象が拡がり、不動産の賃貸借契約もリースと見なされるようになります。店舗を借り受けるための契約は、リース契約ではなく、賃貸借契約の場合が多いと思いますが、賃貸借契約であっても、新リース会計基準ではリース会計対象と定義されることになります。なお、賃貸借契約の内容としてリースに該当しない「保守費」等の費目は除外する必要があります。
-
オペレーティングリースであっても、一部の例外を除いて、全てがファイナンスリースのようにオンバランス処理を求められることになります。オペレーティングリースの場合はリース料を経費として計上します(オフバランス)。これが、ファイナンスリース同様の扱いに変わると、経費計上するのではなく、対象物件をリース使用権資産/リース負債として計上し、それに対して減価償却費と支払利息を費用として計上すること(オンバランス)になります。
このポイントを前項と合わせると「現在、経費として計上している不動産の賃貸料も、資産/負債計上と減価償却費と支払利息を計上して取り崩す」という方法に変わるのです。これは、貸借対照表上の資産/負債が増加することを意味し、欧米の考え方と整合性が取れることになりますが、突然、資産/負債が増えることになり、株主を含むステークホルダーに違和感を与えることにもなります。なお、少額リースと短期リースは従来通り、オペレーティングリースの処理を行うことも可能です。 - 契約期間とリース会計を行うための基準期間の考え方が違います。リース会計を行うための基準期間は、契約書上の契約期間に想定延長期間を加えたものになります。つまり、「初回契約3年、その後3年毎に契約を更改する」という契約の場合は、「3年+3年x契約更改回数」が資産計算の基準期間になります。
多店舗展開企業にとっての3つの重要ポイントを紹介しましたが、「対象物件かどうかの切り分け」「対象費目の切り分け」「リース基準期間の確定」については、監査法人を交えて、契約書情報や関連情報、経営方針をもとに協議しなければならなりません。
新リース会計基準と多店舗情報管理の関係
前置きが長くなりましたが、この章では本題の「新リース会計基準への対応準備として行う店舗情報管理」の重要性をお伝えします。
ポイントは前章を受けた形として「リースの概念が不動産の賃貸借契約にまで拡がることへの対応」「全てがファイナンスリース対応しなければいけなくなることへの対応」「契約期間とリース期間の考え方の違いへの対応」の3点と、「情報の一元管理による次の準備段階への対応」を加えた4点です。
リース概念が不動産の賃貸借契約にまで拡がることへの対応
前章でお話したように「不動産の賃貸借契約であってもリース会計の対象となる」ことは、多店舗展開の企業にとっては大きな影響があります。
最終的に監査法人と物件の対象特定について合意しなければなりませんが、そのために必要なことは「情報の一元管理」です。社内においても、また、監査法人との会議の場でも、一元管理された店舗情報を会議のテーブルにあげて議論しなければなりませんし、紙ベースの情報だけでは議論が空中戦になりかねません。
現在、賃貸借料を含めた店舗に関わる費用を各店舗責任者の管理下でバラバラに処理されている企業も多いと思いますが、情報の入力や更新、利用については各店舗や各部門に任せるとしても、全体はデータベースとしての一元管理が必須です。
なお、企業会計基準委員会(ASBJ)では、リース対象特定のフローチャートを提供しています。
わかりにくい表現を含んでいますので、詳しい情報が必要な場合は当社にお問合せ下さい。
全てがファイナンスリース同様の処理をしなければいけなくなることへの対応
店舗や事務所、駐車場等の不動産では少額契約や短期契約を締結することが稀です。
したがって、現在、賃貸借料として経費処理するオペレーションリース全てが、ファイナンスリースのようにオンバランス処理に移行することはほぼ確実です。
「ファイナンスリース同様の処理=オンバランス処理=資産計上/減価償却計算」ということになりますので、もはや、単純な経費処理では対応できなくなります。
組織の構成上、業務の分散処理のほうが効率が良いという企業もあるかもしれません。しかしながら、今回の変更に対してはデータベースを利用した集中処理が適しています。
もう一点、重要なポイントがあります。
賃貸借契約の中に含まれている費用の内容が不動産だけかどうかの確認が必要だということです。賃貸借契約の中には保守費や清掃費を含むことがありますが、これらを資産計上することはありません。したがって、それは、リース会計から除外し、一般的な費用処理をしなければいけなくなります。
ここにも課題があり、その契約金額について貸主とすり合わせしなければいけないケースが発生する可能性があります。そして、これらの賃貸借契約の内訳もデータベースの要素として登録しておかなければいけないということになります。
契約期間とリース期間の考え方の違いへの対応
前章で「賃貸借契約の契約期間とリース会計の対象期間は違う」「リース期間は契約期間に延長期間を加えたもの」とお話しましたが、これについては、既に、議論の的になっています。
その要因は「延長期間」です。
店舗等の不動産の賃貸借契約においては契約期間を2~3年に定める場合が多いと思います。業界や業態にもよりますが、初回契約の契約期間で契約を満了することは、あまりないのではないでしょうか。
アンテナの役割を果たす店舗やマーケティング調査のための店舗の場合は別として、事業を継続する限り、契約を延長しないことは考えにくく、これは、経営戦略とも関係するポイントになります。
とは言うものの、長期間において契約を延長するという考えをリース会計にあてはめると、貸借対照表上の負債額が膨大になってしまいます。
想像できますように「契約更改を何回とするか」の議論は避けられそうにありません。また、契約書上の解約不能期間や中途解約オプションもリース期間基準計算時に考慮しなければならず、経営戦略を含めた複雑な検討が求められます。
これは悩ましい問題ですが、リース期間が決まらないと資産として計上する額が決まらないので、この点について、監査法人のアドバイスを求めることになります。
情報の一元管理による次の準備段階への対応
2027年4月以降の事業年度からの対応が求められるとした場合、3月決算の会社は2027年3月までに、対象不動産契約の特定、店舗情報管理の業務プロセス・会計プロセスの変更、会計システムの変更をしなければいけませんし、最終的にはそれらの運用がうまく回るかも検証しなければいけませんが、その前に、上記の観点での店舗情報の一元管理ができていないと、何も進めることができないことになってしまいます。
監査法人は「洗い出した契約が網羅的なものか」という視点を持っているので、早期に話し合いを始め、上記の対象費用の切り分けやリース期間について合意しなければなりません。そして、そのためにも、店舗情報のデータベース化が必須要件となるのです。
また、店舗情報のデータベース化は新リース会計基準対応の準備のためだけではありません。今後契約を更新したり、解約したり、新しい契約を締結したりするたびに同様の店舗情報管理業務が発生するのです。その度に情報の扱いを議論していたのでは事業も業務も停滞してしまいます。
今後の適切なリース会計基準への対応のためには、早期の店舗情報データベース導入が最適解になります。
最後に
従来、当社では、業務改善、情報の戦略的利用、社員リソースの有効活用などの点からデータベースを利用した店舗情報管理の必要性をお伝えしてきました。それらの目的がなくなったわけではありません。
しかし、それらに加えて「新リース会計基準という法律への対応」が急務となりました。会計のグローバル化と自社のビジネスモデルとの間に乖離があると感じておられる会社もあるかもしれませんが、今回の変更は避けられないものです。
想定スケジュールでは公表から2年間の準備期間が設けられると思いますが、情報を整理してデータベース化し、それをもとに様々な検討を行い、業務プロセスと業務システムを変更することを考えると、まず、店舗情報のデータベース化を完了させないと、その後に続くタスクを始めることさえできないリスクをお伝えするとともに、「今から始めても、早すぎることはない」とお伝えすることがこの記事の目標です。