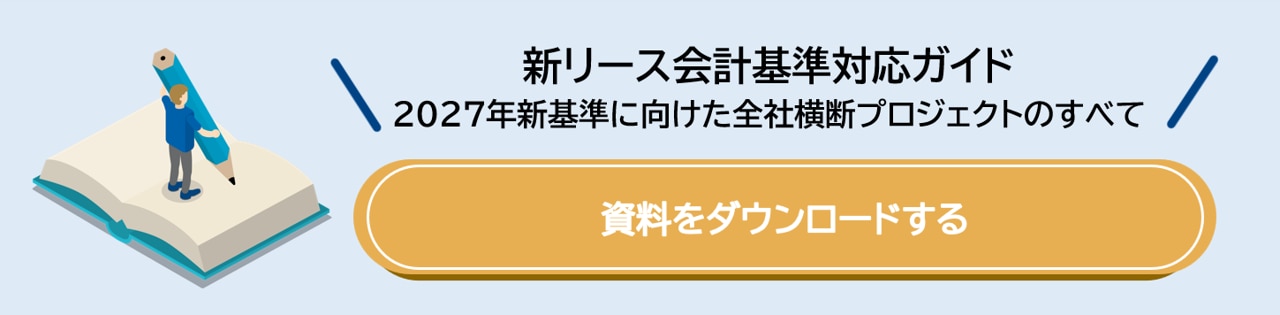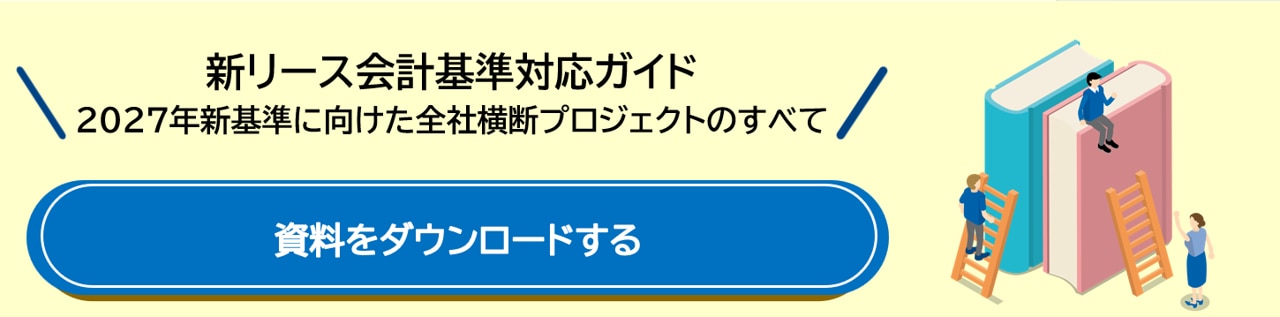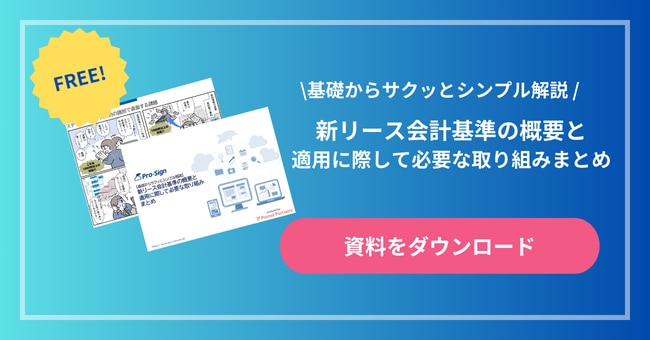新リース会計基準に向けた「部門間の情報断絶」を回避する方法-契約の“全体像”を、把握している人は誰ですか?

2027年施行の新リース会計基準は、従来見過ごされがちだった店舗開発や法務、総務など各部門に散在する契約情報の“断絶構造”を白日の下にさらします。
経理だけでは対応しきれない全社横断プロジェクトとして、誰がどこでどの契約を管理し、どのようにシステムへ反映するのかを明確化するための実践メソッドを解説。
部門間連携の強化による申告漏れ防止からプロジェクト成功の秘訣まで、多店舗展開企業に必要なチェックポイントと事例をお届けします。
目次[非表示]
新リース会計が問う「契約と部門連携」の実態
従来の会計基準では、賃貸借契約の多くは貸借対照表に記載されず、注記での開示に留まっていました。
それが2027年の新基準では、“資産”と“負債”として計上することが義務づけられます。
これが意味するのは、経理部門が単独で済む話ではなくなるということです。
特に多店舗展開企業の場合、店舗開発・営業・法務・総務といった現場や間接部門が契約の起点を担っていることが多く、契約情報が社内に点在しているのが当たり前になっています。
経理も、総務も、店舗開発も。
実は「自社の契約が全部見えている人」は、誰もいない。
ある会社の総務部門はこう言いました。
「社宅や本社のリース契約はうちで管理してますけど、店舗のことまでは把握していません。」
店舗開発部門はこう言いました。
「物件の契約は歴史も長いですし、更新の契約も含めると、数が多すぎて全て把握出来ているかは正直わかりません。」
そして経理部門は、こう締めくくりました。
「つまり、うちの“契約情報の全体像”を誰も持ってないってことですよね。」
2027年に施行される新リース会計基準。
これは単なる会計ルールの変更ではありません。
会社に散らばる契約情報の“断絶構造”をあぶり出す装置でもあります。
店舗契約、設備リース、社宅、ITツール…
“対象リース”は、静かに日々積み上がっています。
厄介なのが、「リース」と明記されていない契約も該当する点です。
多店舗展開企業の社内に存在する契約の一例を挙げてみましょう。
- 店舗の新規出店・更新に伴う賃貸借契約
- 厨房機器や冷蔵設備などの機器リース
- 店舗内什器やレジ周辺のレンタル契約
- 本社・事務所のフロア賃借契約
- 車両リース、社宅の借り上げ契約
- POSやサブスクサービスとセットの「実質的使用権付き契約」
これらが“経理部門に報告されずに現場で処理されている”ケースは少なくありません。
対象契約の網羅が不十分なまま適用初年度を迎えることこそ、最大のリスクです。
「契約台帳があるから大丈夫」では済まされない時代へ
「一応、社内の契約台帳は作ってるから」「Excelでまとめた一覧もある」
— そうした声もよく聞きます。
しかし、“見た目”はできていても、その裏側で起こっている問題に気づかないまま進んでしまうケースも後を絶ちません。
たとえばこんな事例があります。
ケース1:契約台帳に載ってない店舗があった
地方店舗が独自に結んでいた契約が計上漏れに。
監査直前に発覚して修正が間に合わず、四半期決算の開示に影響。
ケース2:法務と経理のリース認識がズレていた
「これはサービス契約だから対象外」と法務は判断していたが、実質的に使用権がありリースとして扱うべき契約だった。
経理が後で気づき、再計算と再評価が必要に。
ケース3:経営層の関心が薄く、プロジェクトが形骸化
必要なリソース(人・予算・システム)が投入されず、最後はExcel手作業で対応。
ミス多発で信頼を損なう結果に。
こうした問題の背景には、「部門間連携の不足」と「プロジェクトとしての設計不足」が共通しています。
「経理だけでなんとか」はもう限界
新リース会計対応は、「一部署の対応」ではなく「全社を巻き込む業務改革」です。
- 契約が発生するのはどこか?
- 情報を持っているのは誰か?
- システムに反映するのはどの部門か?
——この一連の流れに登場する部門は、一つではありません。
- 店舗開発:新規出店・契約更新の最前線。物件情報を正しく拾う役割。
- 法務:契約条項のプロ。延長オプションや変動賃料などのチェックが必要。
- 総務:社宅や備品、社有車など“店舗外”のリース契約の管理者。
- 情報システム:リース台帳や会計システムとの連携・自動化の担い手。
- 経理:計上・評価・開示の最終責任者。
この全体を俯瞰して把握し、どう連携するかを設計しなければ、2027年は「間に合わなかった年」になる可能性すらあります。
実際、成功企業は「1年以上前」から動いていた
ここで参考になるのが、すでに成功パターンを確立している企業の事例です。
ある小売チェーンでは——
- 経理・法務・店舗・システム部門から横断プロジェクトチームを編成
- 契約情報の提出依頼と並行して社内の稟議・支払履歴から契約を逆引きし、漏れを網羅
- システム導入前に一部店舗で試験運用(プレ・トライアル)
- 現場に向けて「なぜこの対応が必要なのか」を丁寧に伝え、協力体制を構築
結果、初年度から混乱なくリース計上をスタート。
経営層にも「これは本当に全社で取り組むべきプロジェクトだった」と評価されたそうです。
その成功の鍵となったポイントとは?
実は、こうした成功企業が重視していたポイントをまとめたのが、今回ご紹介する「多店舗展開企業向け新リース会計基準対応ガイド」です。
本資料は、制度の背景から実務対応、部門別のチェックポイントや、実際にあった失敗・成功の事例までを網羅。
小売・飲食・サービスなど多店舗展開企業に特化した構成になっています。
しかし、ここで中身をすべて紹介することはしません。
なぜなら——
本当に行動したい人にだけ、読んでほしいからです。
タイトルは──
新リース会計基準対応ガイド(2027年新基準に向けた全社横断プロジェクトのすべて)
「なんとなく不安」を、「確信と行動」に変えるために
制度の施行は待ってくれません。
“まだ先”と思っているうちに、2年はあっという間に過ぎていきます。
まずは社内で1回、小さなキックオフミーティングを開くところから始めてみませんか?
その材料として、このガイド資料を活用してください。