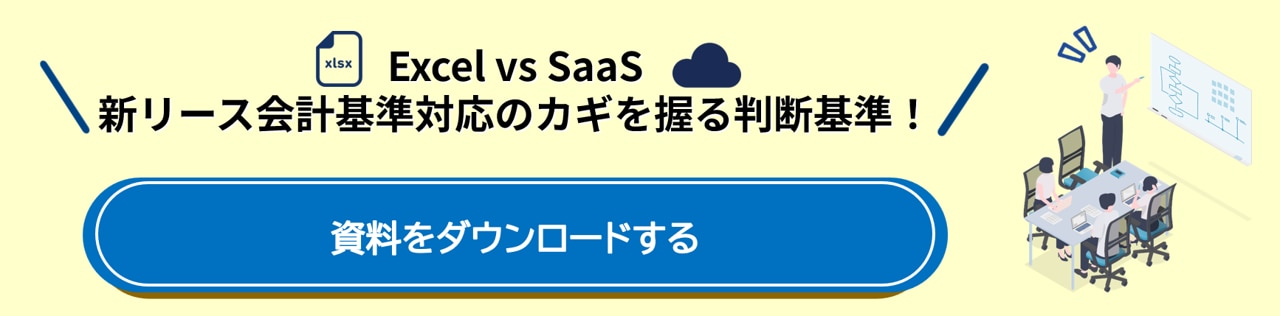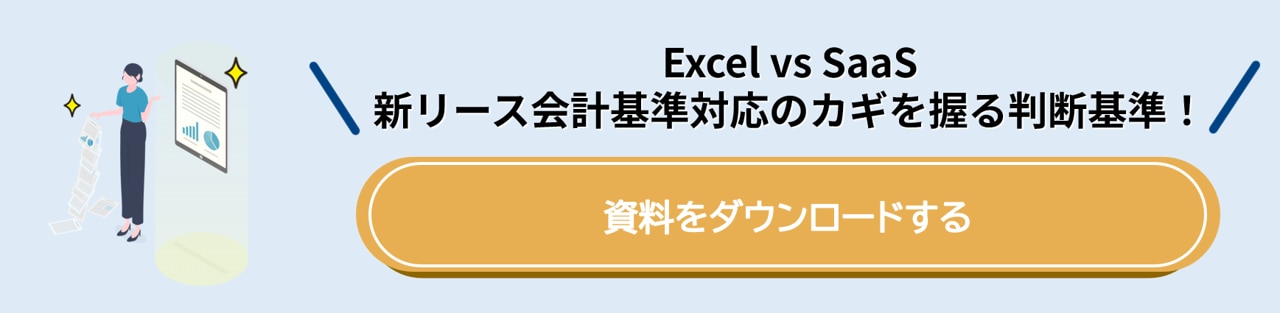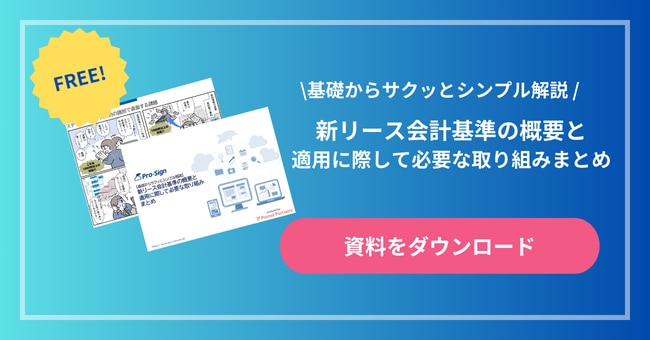【2027年強制適用へ】新リース会計基準で変わる“契約管理”の現場と、いま選ぶべき選択肢とは?

2027年4月、いよいよ「新リース会計基準」の適用が始まります。これにより、企業が締結するほぼすべてのリース契約が貸借対照表に計上されるようになり、企業の財務諸表や内部統制に大きな影響を与えることになります。
とりわけ、多店舗展開を行う小売業・飲食業・サービス業などにとっては、リース契約の数が数百件単位にのぼることも珍しくありません。これまで“経費処理で済んでいた契約”がすべて資産・負債として計上され、計算・管理・監査対応すべてが複雑化する──それが、新リース会計基準の本質的なインパクトです。
目次[非表示]
Excel管理はどこまで持つのか?─現場で起きている静かな限界
実際のところ、現在でも多くの企業がExcelでのリース契約管理を続けています。
従来の会計基準下では、オンバランス対象となるリースが限られており、Excelでの管理でも十分対応可能でした。しかし、新リース会計基準の下では、対象となる契約件数が一気に膨れ上がります。
さらに問題なのが、次のようなExcel特有のリスクです。
- 契約変更のたびに再測定が必要となるが、手計算ではミスの温床に
- 複雑な関数やマクロに依存し、属人化が深刻化
- 監査法人への説明が困難になり、初年度対応の負荷が爆発的に増加
あるIFRS16号適用企業では、Excelで管理していたリース契約の再評価に1年半を要し、結果としてSaaS型のリース管理システムへ移行せざるを得なかったという事例もあります。
「Excel vs SaaS」─その選択に経営の質が問われる時代へ
こうした背景から、今注目されているのがSaaS型のリース資産管理システムです。
ExcelとSaaS、どちらが自社にとって最適かは、契約件数だけでなく、以下のような業務特性によっても大きく左右されます。
- 契約変更の頻度(再測定が年に数回あるか、毎月発生するか)
- リース資産の複雑性(物件以外に車両・什器・設備が含まれるか)
- 監査対応の厳格さ(監査法人・内部監査部門によるレビューの深度)
これらの条件が高度になるほど、Excelでの管理は“属人化リスクの高い綱渡り”となり、SaaS導入の必要性が増していきます。
SaaSを導入することで得られる実質的メリット
SaaS型のリース管理システムを導入することで、次のような効果が期待できます。
- 再測定や契約変更を自動計算で対応し、人的ミスを削減
- 決算処理や仕訳の自動化により、決算早期化・人的工数の削減を実現
- 計算ロジックや履歴の透明化によって、監査対応をスムーズに
- マルチユーザー管理とアクセス制限で、内部統制の強化にも貢献
また、連結仕訳や連結注記まで対応可能な高度なSaaSも登場しており、グループ企業全体での統合管理にも活用されています。
自社にとっての最適解はどこにあるのか?
「うちはまだExcelでなんとかなる」という声は少なくありません。
しかし、その“なんとか”を支えているのは属人化と人海戦術であることが多く、2027年以降の制度対応・監査対応を見据えると、その綱渡りは長く続きません。
だからこそ今、自社の契約数・業務特性・監査体制を見つめなおし、“最適な管理方法は何か”を冷静に見極めることが求められています。
無料ダウンロード資料のご案内
そこで今回、新リース会計基準に向けての実務的な判断をサポートするホワイトペーパーをご用意しました。
『Excel vs SaaS ― 新リース会計基準対応のカギを握る判断基準』
では、以下の情報を詳しく解説しています。
- Excel管理に潜む5つのリスクと、限界の分岐点
- SaaSによる効率化とリスク低減の具体的メリット
- 自社の契約件数・業務特性に応じた判断基準表
- IFRS16対応企業の先行事例と学び
資料は無料でダウンロードいただけます。 下記のリンクから、ぜひご覧ください。