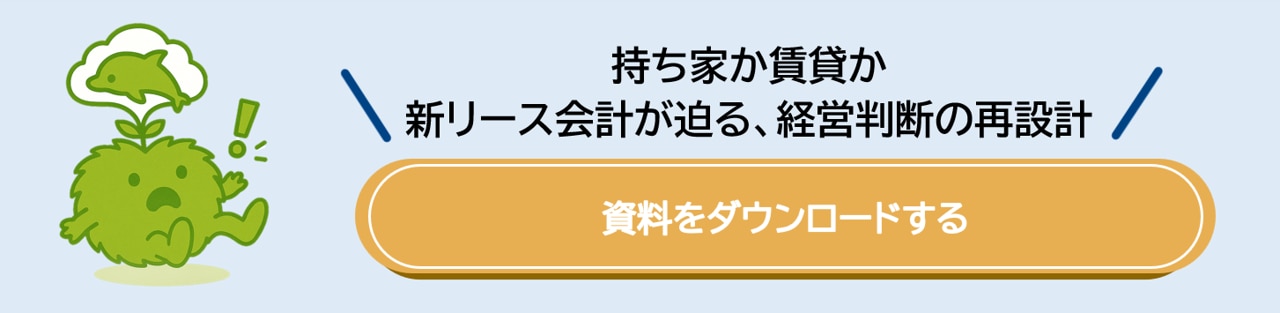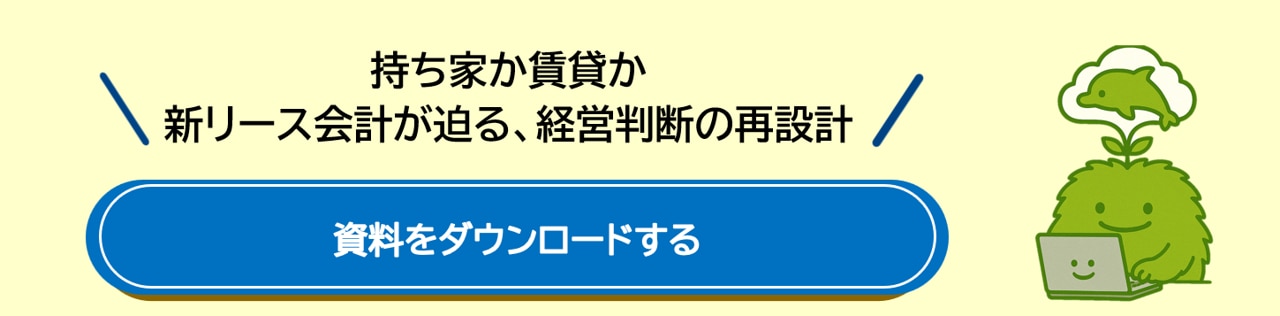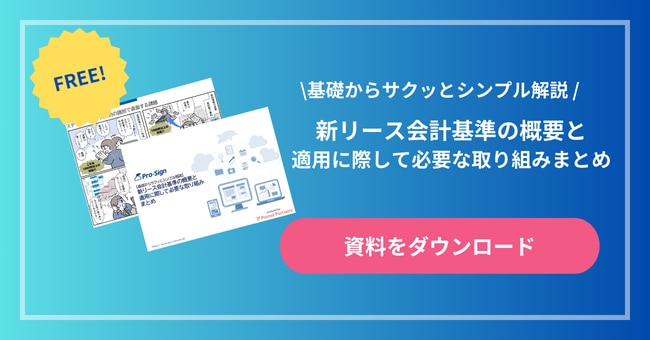経営にも「持ち家 vs 賃貸」論争がやってきた! 新リース会計で変わる資産調達の常識

「持ち家か、賃貸か?」という問いは、多くの人にとって一度は真剣に考えるテーマです。
住宅ローンや家賃、資産価値、ライフスタイルの変化。人生のステージごとにその選択肢は揺れ動きます。実はこの問い、個人の人生設計だけでなく、企業の経営判断にも強く関わっているのをご存知でしょうか?
2027年4月から適用される新リース会計基準のもとで、多くの企業が「借りるか、買うか」という問いに、これまで以上に戦略的な目線で向き合わなければならなくなります。
これは、店舗や設備などの資産調達における「企業版・持ち家/賃貸論争」ともいえるものです。
目次[非表示]
制度変更がもたらす“経営判断”への影響
新リース会計基準では、これまでオペレーティングリースとしてオフバランス処理されていた契約も原則オンバランス処理されるようになります。つまり、見えなかったリースが、貸借対照表上の“資産”と“負債”として姿を現すのです。
この影響で、自己資本比率やROAなどの財務指標が変動し、金融機関や投資家からの見え方が変わってきます。とりわけ多店舗展開企業の場合、数十、数百におよぶリース契約が一挙に財務諸表に影響を与えることになるのです。
今後、リース契約は単なる設備導入や店舗出店の手段ではなく、財務戦略そのものとして捉えるべき対象に変わっていきます。
「とりあえず借りる」が通用しなくなる時代へ
これまでは、初期投資を抑えられる、柔軟に撤退できるといった理由で「リース」を選ぶ企業も多くありました。しかし新基準のもとでは、そうした意思決定が企業の財務状況を大きく左右する可能性を秘めています。
借りた瞬間から、資産と負債が同時に膨らむ。契約内容によっては、その影響は数年、十数年にわたって残る――それが、新リース会計の世界です。
つまりこれからは、「なんとなく借りる」では済まされない。
- 買う方がよいのか?
- 借りるならどの条件で?
- 契約期間や解約オプションは?
そういった問いに、企業として明確なロジックと戦略を持って答えなければなりません。
経営判断を支える4つの視点
個人の住宅選びでも、立地、資産価値、月々の支払い、不測の事態への備えなど、複数の視点から検討するように、企業の「借りるか、買うか」の判断にも複数の軸があります。
特に重要な視点は次の4つです。
- 出店戦略とキャッシュフローのバランス
- 立地と資産価値(将来売却・転用の可能性)
- 契約条件とバランスシートへの影響
- 不確実性に備えた柔軟性の確保
これらの判断軸をもとに、定性的な「なんとなく」ではなく、定量的なシミュレーションに基づいた意思決定が必要になります。
現場で活きる仕組みづくりとシミュレーション
では実際に、どうすればそのような意思決定が可能になるのでしょうか?
鍵は、「契約の見える化」と「数値での再現性」にあります。すべての契約書がきちんと管理され、必要な情報が整理されていること。そして、NPV(正味現在価値)やIRR(内部収益率)といった数値で、借りた場合と買った場合のコストやリスクを比較できる仕組みがあること。
この2つが揃って初めて、経営判断としての「借りる or 買う」が実現するのです。
ホワイトペーパーのご案内
こうした背景を踏まえ、弊社では「新リース会計が迫る経営判断の再設計」と題したホワイトペーパーを作成しました。
本資料では
- 新基準の会計・財務・税務への影響
- 借りる or 買うの判断を支える4つの軸
- 定量的意思決定に使えるシミュレーション手法
- リース契約管理の実務的課題と解決アプローチ
など、実務に活かせる内容を具体例とともに解説しています。
経営にも“住まい選び”と同じ視点を
「持ち家か、賃貸か?」が個人の人生を左右するように、「借りるか、買うか?」という問いは、企業の財務と成長を左右します。
新リース会計基準の施行を機に、経営判断のあり方をアップデートしませんか?