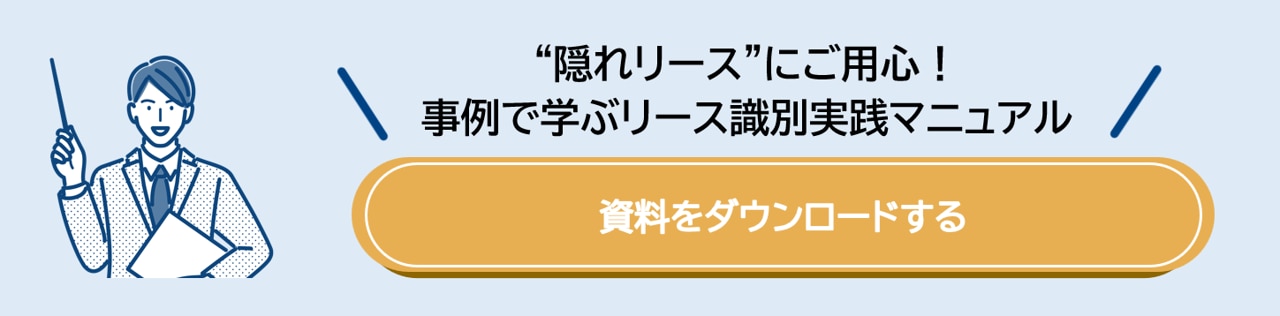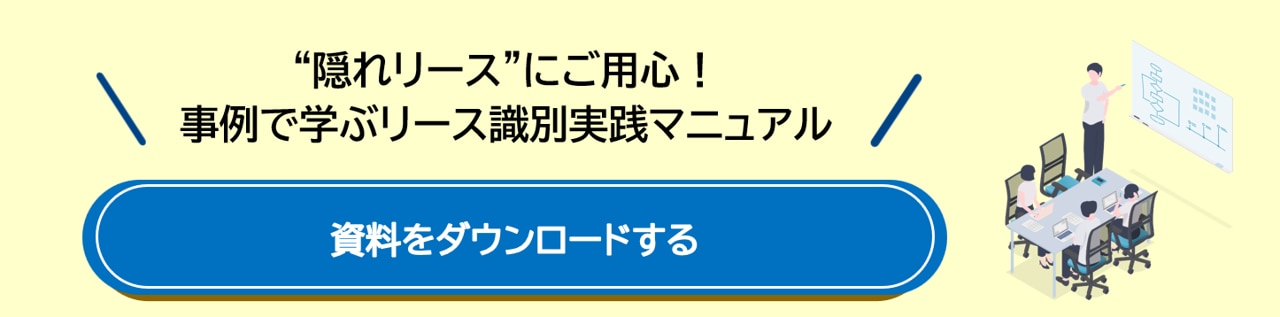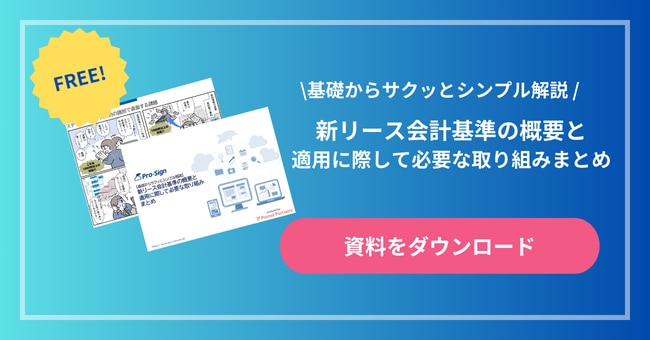「隠れリース」にご用心!― 契約書の奥に潜む“実務リスク”

その契約、「サービス契約だから大丈夫」と思っていませんか?
契約書の表紙に「サービス提供契約」と書いてある。
契約相手は“◯◯サービス”と名乗るサプライヤー、期間は1年未満、金額もそこまで大きくない。
──それ、本当に「リースじゃない」と言い切れますか?
2027年4月に適用される新リース会計基準(IFRS 16等)では、契約の“名前”や“相手先”ではなく、「実質的にリースかどうか」がすべてです。
つまり、「これはサービス契約だからリースじゃない」「短期契約だから対象外」という判断は、完全に見当違いになる可能性があるのです。そしてその“見逃し”が、EBITDAや貸借対照表、監査対応に直接的な影響を及ぼします。
目次[非表示]
「うちは関係ない」は、むしろ“危ない”
私たちが支援してきた多店舗企業の多くが、最初に言います。
「うちは全部サービス契約でやってます」
「基本は1年更新だから、オンバランス対象じゃないですよね?」
「それって資産じゃなくて“利用料”ですから」
……ですが、契約内容を実際に見ていくと、リースに該当するものが次々と出てくるのです。
たとえば、こんな契約。心当たりはありませんか?
- 厨房清掃サービスの契約に、食洗器などの機器が常設されていた
- デジタルサイネージ提供の契約に、ディスプレイ機器の使用権が明記されていた
- フードコートで借りているブースが、「3番ブース」として明確に特定されていた
- 駅ナカ催事スペースを毎年同じ場所で出店している
- 小型POS端末を30台まとめてリースしているが、1台あたりは少額だったのでスルーしていた
- 契約のどこにも“リース”という言葉は出てこないのに、実態は継続使用+支配状態だった
これらはすべて、「最初はサービス契約だと思っていたけれど、よく見るとリース要素があった」というケースです。
そして重要なのは、こうした契約の多くが、出店部門や法務部門の主導で結ばれているということ。つまり、経理がタッチするころには「すでに契約済み」「支払いも始まっている」──
そんな状況になっているのです。
“契約名”ではなく、“中身”を見よう
リース該当性の判断は、以下の2点で決まります。
- 識別可能な資産(Identified Asset)があるかどうか
- 借手がその資産の使用を支配しているか(Use Control)
これらの条件を満たせば、たとえ契約に「リース」の文字がなくても、リース会計の対象となります。
逆に、名前だけ「リース契約」と書いてあっても、自由に交換可能な機器だったり、使用を管理されていたら、リースにならないこともあります。
つまり、新リース会計における識別判断は、“契約の実質”を見抜けるかどうかにかかっているのです。
隠れリースが決算に与える、5つのインパクト
-
EBITDAの変動
リース費用は減価償却+利息に分解されるため、従来の賃料処理と比較してEBITDAが改善するように見える場合も。
-
財務比率の変化
総資産・負債が膨らむことで、ROAや自己資本比率などに影響。
-
監査法人からの指摘リスク
「この契約はオンバランス対象では?」というレビュー指摘で、突貫修正が発生。
-
経営層・IR対応の混乱
財務数値の前提が変わることで、経営指標に基づく意思決定やIR説明にもブレが出る。
-
会計方針の再整備コスト
一度誤った判断で進めてしまうと、後から修正するためのコストと混乱は計り知れません。
リース識別は“会計の話”ではない
ここまで読んで、「うちは経理がちゃんと見てるから大丈夫」と思った方。でも、そのリース判断に必要な情報って、経理部門だけで把握できていますか?
契約の設計・交渉・締結は、出店・法務・総務など他部門が主体。契約書にどんな条項があるのか、どこまで“支配”があるのかは、経理部門だけでは判断しきれない。
リース識別は、「店舗開発」×「総務/法務」×「経理」が横断的に連携してこそ初めて精度が担保されるのです。
「見逃しやすい契約」をどう洗い出すか?
重要なのは、見逃しやすい契約パターンをあらかじめ知っておくこと。そして、「どんな視点で判断すべきか」というチェックリストや観点を社内で共通化しておくこと。
その判断軸をつくるのが、今、このタイミングです。
【無料DL】“隠れリース”を見逃さないための実務レポート
当社では、多店舗展開企業が見落としやすい契約パターンに特化した実務レポートを無料で提供しています。
- リース該当性の判断に迷いやすい契約類型とは?
- 契約書上、見逃しがちなキーワードは?
- 会計・法務・出店部門でチェックすべき“契約構造”の勘所とは?
これから2027年に向けて、“今すぐ手を打つべきリスク”に気づくきっかけとしてご活用ください。
おわりに
リース識別とは、経理処理の話ではありません。それは、「自社がどんな契約をどう結び、どう使っているか」を明らかにすること。
だからこそ、これは財務の話であり、契約管理の話であり、組織の“目の届いていないところ”を照らす話なのです。「うちは大丈夫」と思ったその瞬間に、決算リスクは静かに積み重なっているかもしれません。
- 多店舗展開企業のためのリース識別実務レポート(無料)
- 隠れリースの判断基準/チェックポイント収録
- 現場・法務・経理の連携体制整備にも最適!