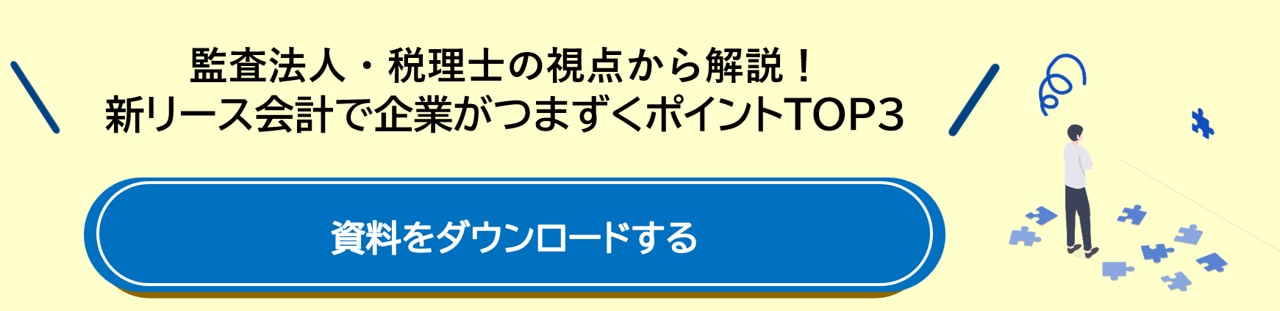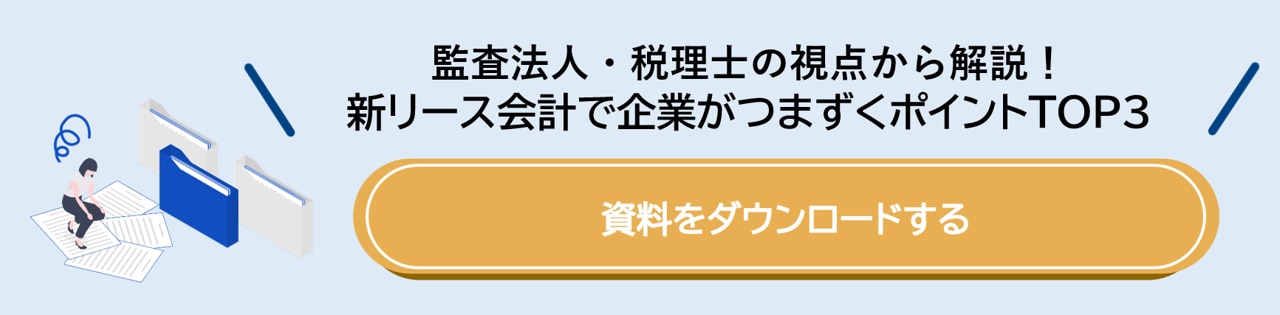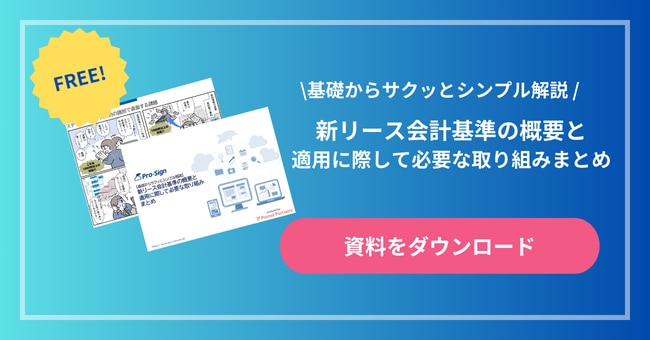監査・税務のプロが警鐘!新リース会計で本当に注意すべき“落とし穴”とは?

2027年4月から適用される「新リース会計基準」。
制度名だけを見ると、「リース取引の会計処理がちょっと変わるんでしょ?」と思われるかもしれません。
しかしこの基準は、単なる会計処理の変更にとどまりません。実態は、契約の見直し、業務フローの再構築、システム対応まで含む企業全体の構造改革ともいえるほどのインパクトを持っています。
目次[非表示]
気づかぬうちに落ちている“3つの落とし穴”
今回私たちは、監査法人や税理士法人の専門家へのヒアリングを通じて、多くの企業が陥りがちな“つまずきポイント”を整理しました。
見えてきたのは、次の“3つの典型的な落とし穴” です。
リース契約の識別・分類ミス
「契約書に“リース”って書いてないから対象外」――その判断、実は危険です。
新リース会計では、契約名称ではなく“実態”で判断されます。たとえば以下のような契約も、リースに該当する可能性があります。
- 店舗の賃貸借契約
- サーバーやIT機器のレンタル契約
- 業務委託契約(特定設備の専属利用を含むもの)
このような契約を見落とすと、監査時に「リースとして計上されていない契約がある」と指摘されるおそれがあります。
リース資産・負債の計算と記録の不備
割引計算、利息・減価償却、契約変更時の再測定…その計算、Excelで本当に大丈夫ですか?
新基準では、リース負債と使用権資産を割引現在価値で算出し、会計処理に反映させる必要があります。
さらに、契約条件が変更された場合は再測定が求められ、処理の複雑さが一気に跳ね上がります。監査法人はこれらの計算根拠を細かくチェックします。
担当者が一人で複雑な関数や手計算に頼っていた場合、ミスのリスクや、説明の困難性が大きくなるのです。
管理体制・システム対応の不足
「リース管理台帳、整っていますか?」
「契約変更、部門間で共有できていますか?」
契約変更の情報共有がされないまま古い条件で会計処理してしまったり、台帳がExcelの個人管理で属人化していたり…。
こうした“地味なほころび”が、監査指摘や申告ミスにつながっています。特に全国展開する企業や複数のグループ会社を持つ企業では、連結修正や社内連携の体制づくりが必須になります。
専門家が語る、「早くやっておくべきこと」
ヒアリングした監査法人や税理士の多くが口を揃えたのが、次の3点です。
- 社内のすべての契約の棚卸し(形式にとらわれず実態でリースを判定)
- 再測定や変更管理に対応できる体制整備
- 専用のリース管理システム導入を早期に検討
すでに海外ではIFRS16号が適用されており、日本国内でも対応に1年半以上かかった例が報告されています。
「そのときが来たら考える」では間に合わないのが、新リース会計です。
無料ダウンロード資料のご案内
“企業がつまずくポイント”をプロの視点から深掘りした実務資料を無料公開中です。
『監査法人・税理士の視点から解説!新リース会計で企業がつまずくポイントTOP3』
この資料では、以下の内容を詳しく解説しています。
- 識別・計算・管理の各フェーズで起きやすい具体的な失敗例
- 監査法人や税理士が実務上、どこをチェックしているか
- システム導入時に重視すべきチェックポイント
制度の理解だけでなく、“実務対応の盲点”に気づける1冊です。
まずはお気軽にダウンロードして、社内の準備にお役立てください。