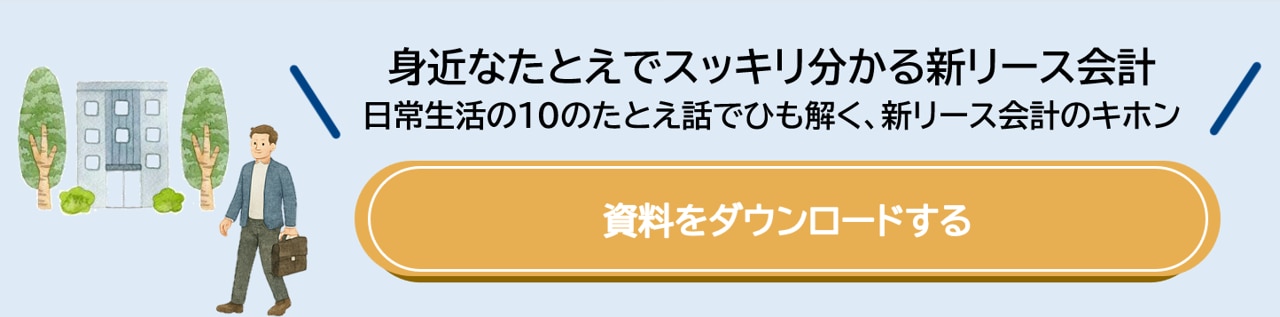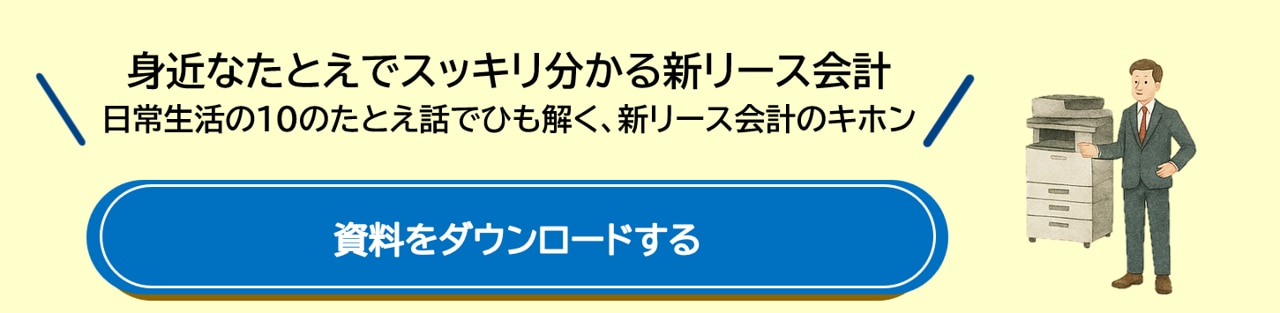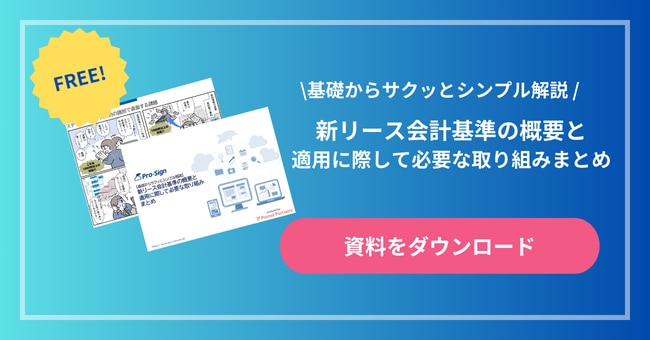【会計初心者向け】新リース会計を“ざっくり簡単に”理解!日常に潜む「あるある」事例で“リース感覚”を身につけよう

「これって、リースになるの…?」
2027年4月から適用される新リース会計基準。会計の知識がないと難しそうに見えますが、じつは“あるある”な日常の契約がヒントになります。
本記事では、会計初心者でもざっくり感覚で理解できるように、よくある契約例をもとに「新リース会計って何が変わるの?」をわかりやすく解説します。
「それ、リースかも?」という気づきが、実務を大きく左右する時代に
会計の話と聞くと、「自分には関係ない」「経理部門の仕事」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、実はこの新リース会計、すべてのビジネス現場にとって“他人事ではいられない”テーマなのです。
その理由は、たったひとつ。
リースかどうかの判断基準が、「契約名」ではなく、「使い方」になるから。
これまでは「これはリース契約です」「これはレンタルです」と、契約書に書かれている名前で処理できることが多くありました。けれど新基準では、「見た目より実態で判断しなさい」という方針が明確に打ち出されます。
「これは本当に、リースじゃないと言い切れる?」
「ずっと使い続けているけど、これって自分たちの“資産”じゃないの?」
そういった問いが、あらゆる部署・担当者に求められる時代がやってくるのです。
目次[非表示]
「これはリースですか?」の迷いが生まれる場面とは?
では、どんなものが“リースの可能性あり”とされるのでしょうか。
たとえば、あなたの会社ではこんな契約に心当たりはありませんか?
- 同じ機器や設備を、何年も変えずに使い続けている
- オフィスや店舗を借りたら、最初から備え付けの什器も使っているが、その扱いが曖昧なまま
- 料金が「無料」とされている装置を設置しているが、関連する消耗品やサービスを継続的に購入している
- 他社では使いまわしできないような、社名入りの特注品をリース会社経由で導入している
- 毎週決まった曜日・時間に特定のスペースを使っている契約がある(例:曜日固定のスペース利用)
これらは、一見すると単なるレンタルや付帯サービスに見えるかもしれません。
しかし、実際の使われ方によっては、会計上“リース取引”として扱う必要が出てくるケースです。
しかも、新リース会計では、それら一つ一つについて
「これはリースになるのか?」
「除外できる要件に該当するか?」
を、契約単位で見極め、判断し、会計処理をする必要があります。
判断力の差が、業務負荷を大きく変える
このように、単なる仕訳作業では済まされない新リース会計の実務。
- 営業部門が交渉したままになっている契約
- 現場で導入したサブスクサービス
- 店舗で継続利用しているレンタル什器
など、すべてが対象になり得る中で、「これはリースかも」と感覚的に気づけるかどうかが、
その後の業務負荷や対応スピードに大きく影響します。
でも──
リース会計を一から学ぶのは、正直、気が重い…
そう思ってしまう方も多いはずです。
実は、身の回りに「リース感覚」はたくさんある
リース会計の世界を、もっと身近に・自然に理解する方法はないのでしょうか?
実はあります。
それは──日常生活にある「リースっぽさ」に目を向けることです。
- スマホの契約
- 家電のサブスク
- 家具付きの賃貸住宅
- 月額制ファッションレンタル
ちょっと使って、ずっと使って、返さずに使い続けて…
「“借りてるだけ”じゃないよな、これ…」という感覚は、誰にでもあるはず。
その違和感こそが、リース判断において最も大切な“実態を見る目”なのです。
会計初心者でも“リース感覚”が自然と身につく一冊、あります
私たちは、そんな「リース感覚を育てる」ためのレポートを作成しました。
タイトルは──
『身近なたとえでスッキリ分かる新リース会計』
この資料では、あえて会計用語を使わず、「え、それもリースになるの?」という10の“あるある”エピソードを通じて、自然とリースの本質が見えてくる構成になっています。
- 会計知識ゼロでも、5分で読める
- たとえ話ベースだから、現場でもすぐ使える
- 「これ、うちにもある!」がきっと見つかる
新リース会計、まずは“感覚”から。
私たちは、形式にとらわれない「実質を見る目」を養うことこそが、新リース会計の第一歩だと考えています。
そして、その一歩は──
意外にも、あなたの日常の中から見つけられるかもしれません。