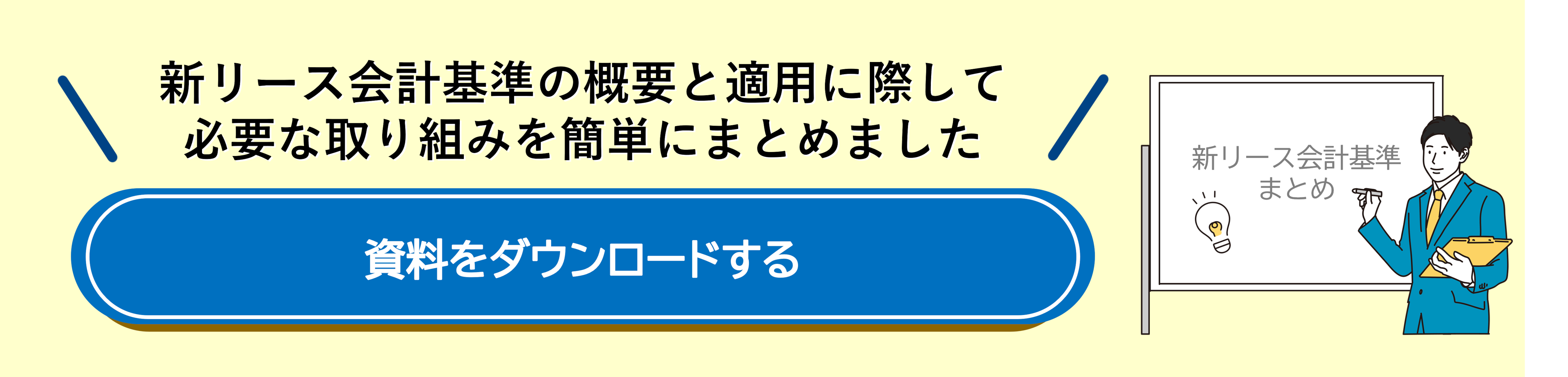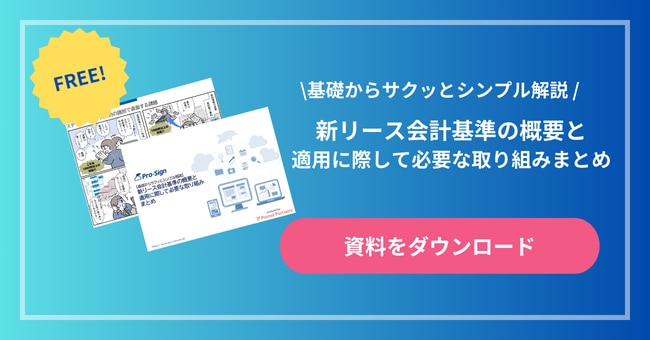経営指標に直撃!新リース会計基準で変わるリース期間の考え方とは

2024年9月13日に公表された「新リース会計基準」(正式名称「リースに関する会計基準」)につきましては、当社のコラム「新リース会計基準の基礎と賃貸借契約に与える影響について」「この契約もリースに該当する?新リース会計で抑えておくべき識別のポイント」でも解説させていただいていますが、この記事ではもうひとつの議論の的になると言われる「リースと識別された不動産賃貸借契約のリース期間はどう定義するのか」というテーマについてお話させていただきます。
2027年4月以降に始まる会計年度から、この基準が強制適用されます。
また、特に不動産賃貸借契約に関しては、リース期間の定義が経営戦略にも関係すると言われています。したがいまして、「リース期間の定義」が多店舗展開企業や事業所向けの不動産賃貸借契約を多く締結されている企業にとって重要なポイントになることは間違いありません。
その理由は、リース期間の定義によっては会社の財務状況に対する評判に悪影響を及ぼす可能性が懸念されることにあります。したがいまして、リース期間の設定には綿密な準備作業が求められます。
なお、新リース会計基準が対象としているものは不動産だけではなく、情報機器や什器などの動産、電力供給契約や情報通信契約等も含まれますが、この記事では、多店舗展開に関わる不動産賃貸借契約に焦点をあてています。
目次[非表示]
- 1.リース期間定義の影響
- 2.リース期間定義の原理原則
- 3.不動産賃貸借契約の種類
- 4.普通借家契約・普通借地契約でのリース期間の考え方
- 4.1.前提条件(延長オプション/解約オプションを含む)
- 4.2.前提条件の分析内容
- 4.3.借り手のリース期間の決定内容
- 5.最後に
リース期間定義の影響
ご存知の通り、新しいリース会計基準では、少額、短期間の例外的な契約を除き、多店舗展開として利用されている不動産賃貸借契約のほとんどがリース会計対象になると考えられます。
では、「不動産賃貸借契約がリース会計対象になること」が「リース期間の設定が議論になること」に、どう繋がるのでしょうか。
従来、不動産の賃料は「経費の支払い」という会計処理、つまり、「オフバランス処理」だけで済んでいましたが、新しい基準のもとでは「オンバランス処理」が求められます。
簡単に表現すると、「賃貸借契約の対象である不動産に対する支払総額を使用権資産として登録し、相手勘定をリース負債として登録する」ことになるのです。
そして、それらは「賃貸借料の支払い(購入想定部分)」「賃貸借料の支払い(支払利息部分)」で取り崩していくことになります。
もうお気づきかもしれませんが、リース期間を長く設定することは、当然、リース支払総額が増えることになります。つまりは、資産/負債額が増えることになるのです。
自社のこれまでの資産/負債額のトレンドが経営的な意思決定以外の力の影響を受け、財務諸表に変化がもたらされるのです。
それは「負債資本比率の上昇」であり、「総資産利益率の低下」であり、「自己資本比率の低下」ということになります。
これらの財務指標の変化は、企業にとって、あまりありがたいものとは言えないかもしれませんが、会計基準のグローバル化を受け入れて、今後は、それを新たな基準点にすると理解すべきかもしれません。
そうは言っても、リース期間をできるだけ短く設定することで資産/負債額を抑えたいと考えることは自然なことです。できれば、賃貸借契約書に記載された契約期間と、設定するリース期間を同一にすることが望ましいのですが、果たして、それは、論理的に可能なものでしょうか。
リース期間定義の原理原則
まず、2024年9月に公表された「リース会計基準」の用語解説で「リース期間」の定義を確認したいと思います。
「リースに関する会計基準」の用語定義の章にある「借り手のリース期間」を要約すると「借り手が契約対象の資産を使用する権利を有する『解約不能期間』に、借り手が行使することが合理的に確実である『リースの延長オプションの対象期間 』と、 借り手が行使しないことが合理的に確実である『リースの解約オプションの対象期間』を合計したもの」という定義になります。
もっと簡単に言うと「契約にある解約オプション、延長オプションをどう使うか」ということになるのです。
自動車や什器、情報通信機器等の動産のリースの場合は、それほど面倒な話ではなく、よほどの例外的な事象がない限り、契約期間内は継続して使用しますし、リース契約満了後は「再リース契約」に移行するか「買い取り」を実施するか、「解約」するかの選択になるのが一般的です。
その内、「再リース」はリース契約期間に含めませんので、ほとんどが「リース契約期間=リース期間」となります。
ところが、不動産賃貸借契約ではそう簡単にいきません。基本的な考え方は「合理的に確実」に、解約するか延長するかの判断であり、その判断基準は次のような「経済的インセンティブ」です。
これらの判断基準をもとに「合理的に確実」に解約するのか、「合理的に確実」に延長するのかを賃貸借契約ごとに決めていきます。
- 契約条件が借り手にとって経済的に有利か(延長した場合のリース料=賃料が現状からかけ離れた上昇とならないか、中途解約する場合に高額な違約金が発生しないか等)
- 賃貸設備の改良、原状回復の要不要(契約対象物件に付随して設置した設備の更新や改良に多額の費用が発生しないか、契約解除時の原状回復費が高額にならないか等)
- 解約に伴うコストや代替物件に対するコスト(契約解除時の諸費用や、別の物件に借り換える場合の諸費用は受け入れ可能な額か等)
- 借り手企業の店舗戦略との合致性(契約対象物件が経営戦略/営業戦略上の位置付けとして重要かそうでないか)
- その他の解約、延長の条件
これらの「経済的インセンティブ」の判断は、企業規模、業種、業態や契約内容によって千差万別ですので、一概に数式やディシジョンツリーのような図式で意思決定の流れを表すことが不可能です。
最終的には監査法人との合意が必要ですが、設定するリース期間は「過去の契約延長実績ではなく、将来予測をもとにすること」と「契約書に定められた期間と同じになるとは限らないこと」を意識する必要があります。
なお、過去において、IFRS対応の対象企業がIFRS16号(リース会計基準)に準拠するにあたり、リース期間をどのように設定したかについては、いくつかのコンサルティング会社がアンケート調査を行っています。
これは、不動産賃貸借契約に限定したものではなく、一般的な動産リースも含んでいますが、結果として、リース期間の設定は業種、業態、企業規模、契約内容、契約対象によって様々だと言えます。
ただし、「契約期間=リース期間にできるに越したことはない」という感想は共通しており、やはり、財務諸表への影響と事務の煩雑化の両方を避けたいという思いがこれらの調査からもうかがえます。
不動産賃貸借契約の種類
不動産賃貸借契約には、普通借家/借地契約と定期借家/借地契約がありますが、リース期間の設定について問題となるのは、ほとんどが、普通借家契約と普通借地契約です。
と言うのも、定期借家/借地契約の場合は、一般的には、契約書に明記されている期間がリース期間となるからです。ただし、例外的に定期借家/借地契約に延長に関する条項が含まれている場合や、中途解約についての条項が含まれている場合がありますので、その際には普通借家/借地契約同様、延長や中途解約が「合理的に確実」かを判断する必要があります。
なお、中途解約の条項がない場合の解約は非常に難しいと考えられます。
これらのことから、リース期間をどう考えるかについては、その対象が、普通借家契約と普通借地契約に限定されることになります。
普通借家契約・普通借地契約でのリース期間の考え方
では、普通借家契約、普通借家契約において、解約するか延長するかの判断が経済的インセンティブをふまえた上で「合理的に確実」であるとは、具体的にどういうことか、例を使って見てみましょう。
ASBJは「リースに関する会計基準」を公表すると同時に「リースに関する会計基準の運用指針」と「リースに関する会計基準の運用指針(設例)」も公表しています。
そして、設例には5つのリース期間設定例を掲載しています(設例8-1から8-5)。
5つの例のそれぞれの構成は以下の通りです。
- 前提条件(契約内容と経済的インセンティブに関係する情報、および、事業におけるその不動産物件の戦略的重要度)
- 延長オプションの有無(8-1のみ)、解約オプションの有無(8-1以外)
- 前提条件の分析内容
- 借り手のリース期間の決定内容
ここでは8-2を取り上げてみます。
前提条件(延長オプション/解約オプションを含む)
- A社(借り手)はB社(貸し手)の保有する建物内に店舗用スペースを借りました。
- 同時に店舗運営に必要であった付属設備を自社で設置しました。
- その設備は10年間使用可能なものです。
- 契約は1年契約で、1年の途中での解約はできません。
- また、更新が可能であり、更新後も市場レートで借りることができることになっています。
- 店舗は営業戦略として、付属設備の一部を5年ごとにリニューアルしなければなりませんが、企業としての経営戦略上は、重要な店舗とは位置付けられておらず、損益状況によっては撤退の可能性があります。
前提条件の分析内容
- 更新後の賃料はリーズナブルであり、延長することは経済的インセンティブの面から「合理的に確実」だと言えます。
- 付属設備に投資を行っているので、延長せずに除却すると損失が発生し、1年で契約を終了せずに更新することが経済的インセンティブの面から「合理的に確実」だと言えます。
- 5年後のリニューアルに伴う対象部分の残存価値の除却費用と追加コストの必要性から6年目の更新は経済的インセンティブの面から「合理的に確実」とは言い難いという評価になります。
- 戦略上、重要拠点ではなく、損益によっては撤退する可能性がありますが、損益が明確でない今の時点で「撤退せずに継続」という意思決定をすることは「合理的に確実」であるとは言えず、6年以上の契約延長は「合理的で確実」より可能性が低いことになります。
借り手のリース期間の決定内容
A社は上記の分析内容からリース期間を5年と設定しました。
なお、上記の例のなかで「店舗が戦略上重要で、損益判断だけでは撤退しない」と定義される場合について、設例8-3として紹介されています。その場合は、リース期間を付属設備全体の入れ替えを行うまで、つまり、10年と設定するとしています。
ただし、その後に、再投資を行って付属設備を入れ替えるかどうかは「合理的で確実」より可能性が低いため、再度の10年更新は行わないというリース期間設定をするという判断をしています。
最後に
このコラムでは、新リース会計基準対応のための不動産賃貸借契約をもとにしたリース期間設定の考え方について解説させていただきました。
キーワードは「経済的インセンティブが合理的に確実とされるリース期間を設定する」ということになりますが、そこには「経営戦略」「営業戦略」を加味することも必要です。
したがって、設定されるリース期間は「数式にあてはめれば割り出される」という類のものではなく、ひとつひとつの不動産賃貸借契約を入念に分析する必要があります。
その分析に欠かすことができないのは「リース期間設定の根拠となるデータ」とその「一元管理」です。また、最終的に監査人と合意するまでの「経済的インセンティブ検討の履歴」を残すことも重要になります。
また、上記の例のように、付属設備への投資もリース期間設定の意思決定に関わることもあるため、「不動産の関連情報」も管理すべきです。
当社の「Pro-Sign多店舗展開企業向けオリジナル店舗マスター」はこれらの要件をすべて満たす機能を有しています。是非、ご利用をご検討いただき、早期の準備にお役立てください。