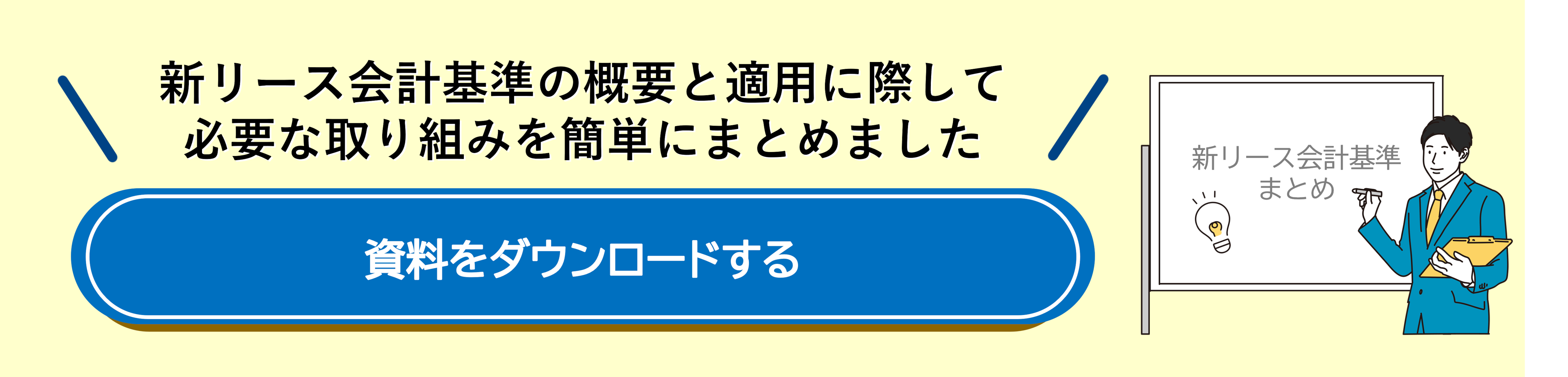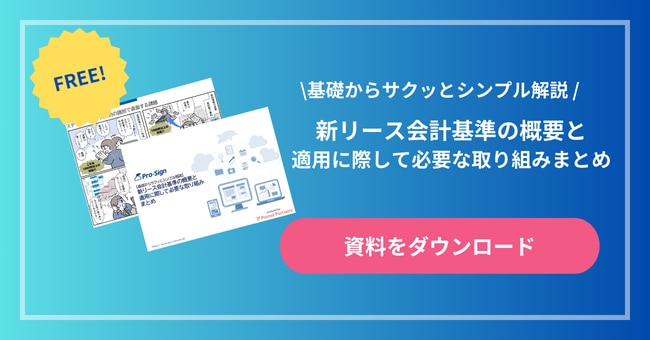「使用権資産総額の重要性が乏しい」とはどのような場合?新リース会計基準で設けられる例外措置について解説

新リース会計基準に簡便な対応ができるように「使用権資産総額の重要性が乏しい場合」の措置が考えられています。これにより、事前の準備作業や会計的な運用業務の負荷が大きく軽減されるかもしれません。
当コラムでは、「使用権資産総額とは何か」「重要性が乏しいとはどんな状況をさすのか」、そして「そのために考えられている簡便的な措置とはどういうものか」「それは何のために考えられたのか」という視点と、それとは逆に「簡便的な措置が使えない状況」という視点の両方で解説を進めて行きます。
目次[非表示]
「使用権資産総額」が表すもの
当コラムは「使用権資産総額の重要性が乏しいと認められる場合には、例外的に簡便な会計処理を行うことができること」の解説を目的としています。とはいえ、そもそも例外ではない本来の会計処理とはどんなものでしょうか。まず、それを確認しておきたいと思います。
企業会計基準第 34 号「リースに関する会計基準」(いわゆる「新リース会計基準」)に従って、リースと識別された資産は、同じく新リース会計基準の第38項、第39項にあるように「利息相当額部分とリース負債の元本部分に区分し、前者を支払利息として会計処理し、後者を元本返済として会計処理する」という考え方になります。なお、未払い部分のリース料総額は使用権資産とリース負債という形で貸借対照表上に登録され、最終的に減価償却費によって償却されます。
つまり、これが「オンバランス処理が求められる」という意味になるわけです。従来、オフバランス処理をしていたものをオンバランス処理に変えることは大きな業務的な負荷を意味します。(オンバランス処理については、当社のコラム「この契約もリースに該当する?新リース会計で抑えておくべき識別のポイント 」でも紹介していますので、ご一読下さい。)
では、例外として簡便に会計処理を行う条件である「使用権資産総額の重要性が乏しいと認められる場合」と言う文言の「使用権資産総額」とは何でしょうか。
それは、未経過のリース料の期末残高の総合計を意味します。つまり、リース契約(以降の文では、サービス契約の中に含まれるリース部分も、全て「リース契約」と簡略化して表現しています)や不動産賃貸借契約によって今後支払うべきリース料の期末残高合計であると言えます。
この「使用権資産総額」を算出するためには、まず、リース契約、および、不動産賃貸借契約を洗い出して、リースと識別されるものの使用権資産計上総額を試算する必要があります。
「重要性が乏しい」という定義の意味
では次に「使用権資産総額の重要性が乏しい」という記述の中の「重要性が乏しい」という表現について考えてみましょう。
新リース会計基準適用指針の第41項には「(重要性が乏しいとは)未経過のリース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が 10 パーセント未満である場合をいう」とされています。
簡単に言うと、リース契約や不動産賃貸借契約によって今後支払うべきリース料の残高合計(つまり使用権資産合計)が、企業全体の資産の10%を下回るとき、そのリース資産は事業全体に対して大きな影響を与えず、重要性がないと判断されるのです。
計算式で言うと、実際の保有資産総額と使用権資期末残高の合計額を分母とし、使用権資期末残高を分子とすることになります。
ただ、上記の定義に合致するかどうかについて、簡便法を適用しようとする企業では、新リース会計基準適用当初だけではなく、毎期の確認が必要となります。これは、意外と大きな業務負荷になると想像されます。
この定義に相当して、例外的な簡便法を適用することができる企業は「分母である自社保有資産が大きい会社」か「分子であるリース資産が非常に少ない会社」で、かつ「その値の変動が少ない会社」と言えます。
なお、混同しないように付言致しますと、今回の10%基準の計算は「使用権資産総額」をもとに行います。これは会社のリース資産全体についての検討であり、個別の契約内容に対するものではありません。故に、「会社全体の資産の中で、リース資産が比較的少ない(10%未満)場合は、リース資産の重要性は乏しいと考えられるので、簡便的な処理をして良い」というものです。
一方で、個別の契約内容に対するものは、「短期リース」や「少額リース(300万円以内)」という例外措置が設けられています。個別契約に関する解説について、詳しくは当社コラム「オンバランス処理とは?新リース会計基準に関する4つの用語解説」をご覧ください。
使用権資産総額の重要性が乏しい場合の簡便法
さて、例外としての簡便な会計処理法の説明の順が後になってしまいました。
例外的な会計処理方法は、新リース会計基準適用指針の第40項に記載されており、二つの選択肢を提示しています。
- リース料から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法です。
ここで言う「合理的」とは、前述の「『使用権資産総額』が表すもの」の章で紹介した「利息相当額部分とリース負債の元本部分に区分」するための「利息相当部分の計算」を意味し、その複雑な計算を行う必要がありません。
したがって、使用権資産、およびリース負債はリース料総額をそのまま計上することになります。また、減価償却により、リース期間満了時には残存価値がゼロとなるように設定する方法です。
これにより、利息相当部分の計算が簡略化されます。なお、実際に支払うリース料も分割せず、そのまま費用計上します。(詳しくは新リース会計基準適用指針の設例9-1の②をご覧ください)。
- (1)とは違い、利息相当額を「合理的に」計算する必要はありますが、その総額をリース期間中に定額で配分する方法です。
つまり、この方法では、実際に支払うリース料を元本部分であるリース負債額と定額で配分された利益相当額に分けて費用計上する必要があります。
なお、使用権資産、およびリース負債は利益相当額を除いた額で登録され、減価償却により、リース期間満了時には残存価値がゼロとなるように設定されます(詳しくは新リース会計基準適用指針の設例9-1の③をご覧ください)。
簡便法利用のメリット/デメリット

このように例外的な会計処理は、新リース会計基準がもたらすであろう業務負荷を削減することが可能です。特に、小規模企業において会計業務が複雑化することはコスト増にもつながりますし、業務の遅滞を招きかねません。新リース会計基準もその点を考慮した形となっているのです。
とは言っても、10%基準を満たすかどうかのシミュレーションは避けることができないものです。
リース契約、不動産賃貸借契約の情報の一括管理はどうしても必要になります。
なお、この例外措置は「外部から見た場合、使用権資産の経済的実態がわかりにくくなる可能性」「財務諸表上に使用権資産、リース負債が表されないため、他の企業との比較が難しく、投資家からみた判断材料が不十分になる可能性」というデメリットを意識する必要があります。
簡便法が利用できるケースと利用できないケース
ここで、簡便的な会計処理が可能となる企業形態を考えてみたいと思います。
例えば、製造業など、多くの設備や大きな土地、建物が必要で、かつ、それらを自社で保有している場合、設備に組み込むソフトウェアの使用権が主な使用権資産となるケースが考えられます。このような企業では、その使用権資産の影響は限定的となるため、事業規模が大きくても使用権資産総額が10%基準を下回って、簡便法の対象となる可能性があります。
ただし、極端な場合、設備、土地、建物等の資産がすべてリース契約下にあるとすれば全資産における使用権資産の割合が10%以上となり、簡便法の対象外となる可能性が高くなります。
この例外措置は、リース契約や不動産賃貸借契約を通じて利用している資産の総額が、その企業全体の資産規模から見て非常に小さい企業を対象としています。
その点から考えると、多店舗展開が積極的であればあるほど該当しにくい例外規定かもしれません。ただ、不動産賃貸借契約の管理や分析は、この例外規定のためだけに行うものではありません。契約を管理していく中で、付随的に10%基準に関わるようなケースが出てきた際には、ここでの情報を是非参考にしていただきたいと思います。
最後に
「使用権資産総額の重要性が乏しい場合に可能となる例外的な会計処理法」について、表現をひとつずつ分解しながら解説させていただきました。
結果的に例外措置が適用できるかどうかは各企業の状況によりますが、ともあれ、「動産リース契約、不動産賃貸借契約、サービス契約を洗い出す」→「それぞれの契約がリースを含むかどうかを識別する」→「リース期間を定義する」→「対象外となる基準(少額リース、短期間リース)に該当するかを確認する」→「リースを構成する部分と構成しない部分の区分する」というステップが必要です。
ここで、紹介させていただいた「使用権資産総額を計算する」はその後に続くステップであり、10%ルールに該当するかどうかは、その結果としてのみとらえることができるものです。そして、それらすべてのステップの基礎は契約情報のデータベース化にあると考えます。
当社のPro-Signは専門のコンサルタントが持つ知見と情報を集約し、不動産賃貸借契約の効率的なデータベース化のために開発されたSaaSシステムです。
詳しくは、ぜひ当社までお問い合わせください。